旅日記なおきん
ラマダンのまっただ中にアルジェリアに行くとどうなる?
イスラム教には年に一度、1ヶ月ほどの断食月がある。
食べたり飲んだりすることで、人間は身体を満足させているが、それで弱くなるものがある。それが魂である。だから弱くなった魂を回復させる月を9月と決めた。天からアラーの神が魂を満たすありがたい月であると。ラマダン。いまじゃW杯のアルジェリア選手が心配されたことで、すっかり日本人にもおなじみとなった。
コーランのいう9月は太陰暦のそれだから、太陽暦だと誤差がある。それで毎年この1ヶ月の期間が変わり、2014年は6月28日から7月27日ということになった。全世界のイスラム教徒たちは、この教えに従って断食をおこなう。水を飲んでもいけないし、性行為もダメである。だけど丸々一ヶ月飲まず食わずでは死んでしまう。それで、太陽が出ている時間だけ適用される。つまり日の出から日の入りまでの時間帯は、食べても飲んでもならない。
イスラム国のであるアルジェリア。
そこへ行こうと決めたとき、ラマダンのことはまったく頭になかった。気付いたあとも、まあ自分は異教徒だから関係ないだろうとタカをくくり、それでも心配だからと持たせてくれた少しばかりの食料をスーツケースに忍ばせた。
飛行機が同国の首都アルジェにぼくを運び、タクシーで市内のホテルまで着くあいだ、町中の店という店のシャッターがおりていることにぼくは気づく。街に人はいる。車もガンガン走っている。だが正午にもかかわらずレストランやカフェはどこも固く店を閉じて、人の気配がまったくない。ぼくは機内食を食べなかったことをさっそく後悔し始めた。
▲ 町のレストランは全部しまっていた
ホテルの部屋に荷物を置くとすぐに、ぼくは水とパンを求めて街をさまよう。近くにキオスクがあった。ありがたい、水が売っている。勘定をすませ、さっそくペットボトルに口をつけようとすると、店のおじさんからどなられた。「ラマダンだ!」
部屋に退散し、やっとのことで喉を潤しながら、ことの事態にようやく気付いたのだった。ラマダンは異教徒にも容赦ないのだと。時計を見る。午後2時。日の入りまであと6時間もあった。ホテルのレストランですらこの開くのは20時からのようだった。
街をぶらぶら歩く。
いつものように町のヘソをおさえ、おおよその方向をつかむ。アルジェの街に市電はなく、市内の移動は申し訳程度のバスと、タクシーくらいしかない。カミュの「異邦人」にはフランス統治時代のアルジェの街には市電が登場していた。それが今はない。歩くことにした。坂が多く、通りと通りのあいだには長い階段で結ばれていた。この街で過ごすには健脚であることが必須である。しかもラマダンである。陽を避け水分を補給しようにも、水は飲めず逃げこむカフェはシャッターがおりている。
2時間くらいフラフラしてパン屋を見つけた。丸いやつと長いやつ、ひとつずつを80ディナールで買い、部屋に戻ってむさぼった。カスバの中にある市場でバナナやネクタリンを買い、翌日のランチにした。あとでカスバは警官同行でないと一人で歩いてはいけないことを知った。危険地帯なのだと。それじゃ映画「望郷」のころと変わんないじゃないかと。ぼくはいろんなことを後になって知る。それなのに、寄ってくる悪ガキどもと一緒に記念撮影したりしながら遊んでいたのだ。
▲ ようやくパンを手に入れた
▲ ある日のランチ(バナナは1本)
▲ ある日の朝食、コーヒーとミルクをそれぞれ温め、同時に注ぐフランススタイル。
ようやく日が暮れた。それを合図に、いつの間にか街角から人々の姿が消えた。うるさいクラクションもなっていない。通りから車が消えている。うじゃうじゃいてぼくが建物の写真を撮るたび、いちいち警告していた警官の姿もない。まとわりつく子供たちの姿もない。頭の上の鳩が飛び、’猫が一匹、脚に顔をすりつけてきたがそれが通りに残る生き物のすべてだった。アパートのあちこちから談笑する声が聞こえ、食器がカチャカチャとなるのが聞こえた。
▲ 人々が消えた日の入りの一瞬。
シャッターを開けたばかりのレストランでは、入口そばのテーブルで店の親子が食事の最中だった。「開いてるか?」と聞けば「ああ、中に入っておいで」と合図してくる。10歳くらいの店の子が水を一本、テーブルにでんと置き、「ニーハオ!」と挨拶してくる。アルジェでは、中国人の方が日本人よりずっとメジャーなのだ。道ゆく誰もが、そのようにして中国語で挨拶してくる。それが少し気に入らなかった。「悪いがぼくはジャポネだ」と目の前で手をひらひらさせ、「ジャポネにはなコンニチハ!」って言うんだよ、と訂正させた。
腹が減るとなにかと機嫌が悪くなる。
ジョルバという麦の入ったトマトの煮込みスープ。ラム・シチューのタジン。たっぷりのバケット。これが
ラマダン中、どこの店でも出されるメニューだ。旅行者だからといって他の選択肢はない。
ベジタリアン用の別のスープが用意されているくらいである。宗教であり、慣習である。異邦人に異論は挟めない。しかも高い。足元をみた
ラマダンプライスである。味も美味いが商売も上手い。ただ、旅行中はずっとこればかりだと思うといささか気が重かった。
▲ ラムのタジン
昼間、
ノートルダム寺院に行きたくて、各ブロックに必ず一人はいる警官に道を尋ねた。相変わらず言葉は通じないが、次々に警官がやってきて、ただの旅行者相手に5人がかりで道を教えてくる。そのうち一人がぼくの口を指差し「
ラマダン中だぞ」と注意してきた。自覚はなかったが、ぼくはガムを噛んでいたのだ。ここは
シンガポールかよ!ぼくはティッシュにガムを吐き出し、くるんでからそのティッシュを警官の鼻先へつきだした。警官は一瞬ひるみ、なんだこれはと苦笑い。
ぼくの、ささやかな抵抗であった。
▲ 街のあちこちで見かける警官たち


















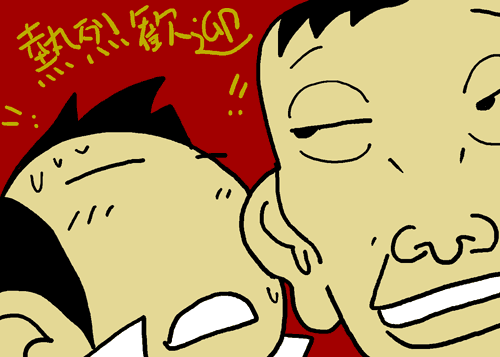


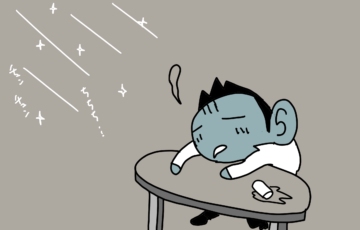
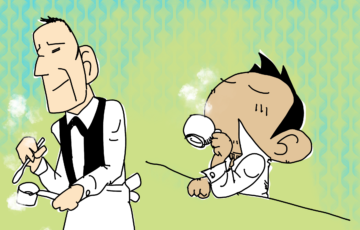
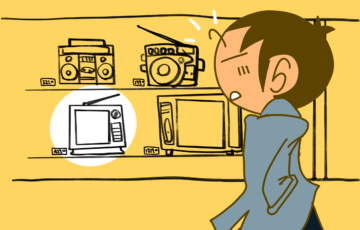
最近のコメント