
ガイドは左、ラクダ氏は中央の人物
ガイドは一枚の紙を広げてみせる。
ツアーの日程表である。ぼくが行きたかった場所はことごとく「×」のマークが書き込まれていた。ちょっと待ってくれ、とぼくは言う。そこに行くために日本からはるばる来たのだ、と。彼はそれは悲しそうな顔をしてみせ、「WARなんだよ」と言う。このベニ・イズゲンとボウ・ヌーラとの間の抗争がひどく、警察が立ち入りを禁じているんだ。あなた、そこ、行けない。行ってはいけない。
「そこをなんとか(Could you try to make it, please!)」と、ぼくはガイドの膝をぽんぽんと叩く。彼は困った顔をして何処かへ電話をかけ、しばらく何か喋っていたが、あらためてぼくの方へ顔を向け、「Try してみた、でも無理だよ」と首を振りながら言った。

ガイドの書いたメモ。英語は文法的には無茶苦茶だが、意味はわかる。メリカ;× 、ボウ・ヌーラ;× 、ベニ・イズゲン;× 、エル・アティーフ;× とあり、そこは WAR状態で問題あり。とある。

ぼくの「行きたいメモ」。ある意味、今日の打ち合わせの議事録でもある。ガイドはぼくのイラストをみて、「なんでこんな口なんだ?」と笑う。ラクダ氏は「こんな口かい?」と真似をしてみせる。まさにラクダそのものだった。似すぎて逆に笑えない。
世界遺産にもなっている、いわゆる「ムサブの谷」と言われる一帯は、ここガルダイア県に含まれる幾つかの村をさす。敬虔なイスラム教徒としての戒律を厳しく守っている人々がそこに住んでいる。外国人の宿泊は禁じられ、酒もタバコもダメである。立ち入るには、必ずガイドを伴い、人物の撮影もできない。女性が外出するときは必ずチャドルをかぶり、片目しか出さない。フランス統治時代ですら、これを排除し伝統を守り続けた自負もある。だから独自の文化や慣習がそのまま残り、他に例を見ない独特の景観がそこにあった。皮肉なものである。排他し続けた結果、それが異文化の人たちには魅力に映るのだから。

メットリリの広場。暑い。
ベルベル人のムサブ族。日本ではまだ鎌倉幕府も開かれていない1013年に、ここをオアシスとして開拓し、水脈を確保し井戸を作り集落をこしらえた。その最初の村をエル・アティーフという。今回は頼みこんで、なんとか訪問することができた村である。

エル・アティーフの町



フランス建築界の巨匠、コルビュジェのキュービジムに影響を与えたムサブの建築

町のガイドさん、案内をし、同時に外国人であるぼくを監視している。人物にカメラを向けるとすかさずNGを出してくる。

人物が写っていないのは、そんな理由である。とくに女性。白いチャドルを頭からすっぽりかぶり、片目だけ出している様相をぜひ撮りたいところだけど、絶対に許されないのだ。ぼくも敬意を払って写さなかった。

とはいえ、写り込みそうなときもある。女性はぼくの存在に気づくと、さっと身をかわし、背を向けて立つか、民家に隠れる。こうしたことがくりかえされるうち、自分がなんだか不浄な存在であり、存在してはならない気がしてくる。
エル・アティーフだけではかわいそう、ということで、40km離れた「メットリリ」という街にも訪問させてくれた。ここはやや戒律がゆるく、異教徒にもある程度寛大で、おまけに今回の抗争には巻き込まれていない。「尖塔があるし、オアシスもある。おすすめだよ」とガイドは胸をはる。

メッ
トリリの町の入り口付近。女性は黒いチャドルで、エル・アティーフの白チャドルに比べ、少し俗度が上がる感じだ。


古い家でも もちろんエアコンは装備されている。

緑の蔦が、目に優しい。


1時間以上、この辺りを歩いていると、ある種の「酔い」のようなものを感じた。ただの熱中症だったのかもしれないが。何しろ炎天下のにもかかわらず、一滴の水も飲めないのだ。おそるべしラマダン。


市場が開かれていた。中央の人物こそ、ラクダ氏である。なぜか正面からの写真は許してくれなかった。

中には立ち入れなかったベニ・イズゲンの遠景。まさにキュービズムの集合体である。

他に例を見ない独特のミナレット。尖塔部分にはスピーカーがあり、夜になると緑色の明かりが灯る。それが不気味で、まるで異星の生き物のように見える。
とくに危ない目には遭うこともなく、ラクダ氏の運転するシボレーは無事、ホテルに到着した。町の至るところに警官と車両があり、透明な盾とヘルメットをかぶった機動隊員が待機しているところも見られたが、戦闘はついぞ見かけなかった。同時に自分以外の観光客にも出会わなかった。あとでフロントのスタッフに話すと、「ラマダンだからね」と言う答え。戦闘もなければ、観光客もいない。平和なラマダン。「でも、年中ラマダンだったら、あんたら失業しちゃうんじゃないの?」 とぼくが言えば「アッラーがそれを望むのなら」と返してきた。
彼らもやはり、ムサブの末裔であった。





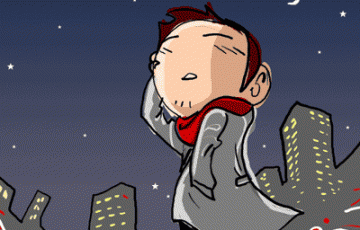






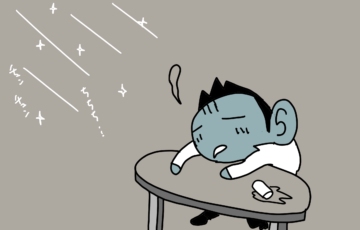
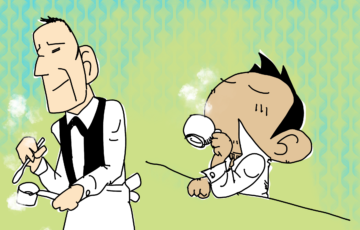
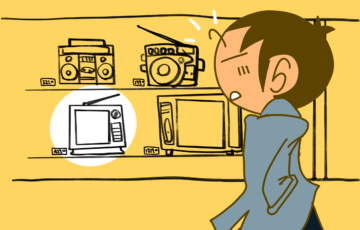
最近のコメント