
全記事に続き、カンボジアについて書きます。
正直言って、ここを訪問したことを少し後悔しています。あまりにも強烈だったから。ただの興味本位で行くところではないなとつくづく思います。記事としてここにアップすることもずいぶん逡巡しました。それでもあえてアップしたのは、あれほど穏やかでおとなしく、親日的で気配りも細やかなカンボジア人が、なぜたった3〜4年の間だけ突然狂ったように自ら同胞を貶め200万人も虐殺をする暴挙にでてしまったのか?そのことについて、一度思案してもらえればと思ったからです。これは人間普遍の狂気なのか。それとも・・?
1975年4月17日、ポルポトは建国してわずか5年という短いクメール共和国を倒し、民主カンボジアを樹立した。それに伴い長かった内戦も終わり、国民の間に安堵がもれた。だが新しい国によって自分たちが、まさか内戦のときよりもひどい目に遭わされるとは、このとき思いもよらなかったにちがいない。
ポルポト書記長はさっそく原始共産制の旗を揚げ、実行に移した。政治、経済、法律、医療、教育、宗教・・かつてあったものを全部否定し、関わっていたものを探し出しては殺していった。世にいうカンボジアの悲劇はこのようにして始まった。
1945年の日本は、ある意味1975年のカンボジアよりずっとひどい状況だったが、戦後急速に回復し、たちまち戦前のレベルを超えて経済発展を遂げ世界第二位の経済大国となった。アメリカの占領政策がよかったからだという人もいるが、頭脳(=人的資源)と精神的支柱(=天皇制)が残されていたからともいえる。
ポルポトは王政を廃止し、都市に住む人たちを農村の労働キャンプに送りこんだ。「都市と農村の格差をなくす」がスローガンだからだ。それなら都市人口をなくし資産を奪えばいい、というわけだ。首都プノンペンも空っぽになった。水道や電気が止まり、通りから人が消え、使えなくなった紙幣が風に舞う。
だがまったく人がいなかったわけではない。市内にあるいくつかの政治犯収容所では、反革命分子と呼ばれる人たちの粛清がおこなわれていた。粛清とは、自分たちを脅かすことになるであろう敵を、あらかじめ消してしまうことである。だがポルポトには別の目的もあった。自分たちの失敗の責任転嫁である。
ポルポトと彼が率いるクメールルージュは、経済やインフラ、寺院などを壊し、教育を受け見識、良識のある人々をかたっぱしから始末した。原始共産制がもつ理念のジャマになると。まともじゃない。たちまちそのあおりを食らうことになる。樹立後わずか1年足らずで飢餓や疫病が発生し、国家再生の計画が遂行できなくなっていたのだ。計画が遂行できなくなれば、中国からの支援も止まってしまうかもしれない。悔い改めるのは自分たちのほうだったが、こうなったのも反革命分子のせいだとし、あらためて反革命分子狩りに乗り出したというわけである。
もちろん、本来の反革命分子などとっくに処刑してしまっている。だが裁判もかけていなければ調書もない。つまり処分したという証拠がない。中国に対しては「こいつらのせいです」と革命が阻害されていることを立証し、援助を継続してもらう必要があった。各国に広がる暴力革命の成功は中国の望むところだった。(日本もその標的だったことはあんがい知られていない)
捕まえた人々を殺すのにためらいはない。
キリングフィールドでは日常茶飯事のこと。殺すのは簡単。だがその前にひと仕事やってもらう必要がある。捕まえてきた者たちに「自分がその反革命分子だ」と自白させ、革命のじゃまをして国を混乱に貶め、飢餓を招いたことを自供してもらうことだ。それで「いかにも革命に逆らいそうな人々」を全国から集め、収容していった。
なぜ自分が捕まったのかよくわからない人たちは、まず固い鉄の椅子に座らされ、写真を撮られた。それがただの記念撮影でないことくらいわかる。抵抗すればたちまち暴行を受けるからだ。プノンペン市内にあるS21(トゥール・スレン)虐殺博物館には、この時撮られた写真が壁一面にずらっと並ぶ。中には殴られ顔が腫れあがっている写真もあった。しばらくして「処刑後」の写真も撮られたが、もちろん本人の自覚はない。
ここで収容された人は3年弱でその数2万人といわれる。元政府高官の家族もいれば、ただの学生もいた。この施設はかつて高等学校の校舎を改造したものだから、通っていた生徒もいたかもしれない。
収容者への尋問は熾烈を極めた。
求められない答えを返せば高圧電流が流された。スパイじゃないと訴えれば拷問を受け、切れた唇でスパイだと告白すればやはり拷問を受けた。そもそもやった覚えもないから、記憶の中に答えはない。痛みから逃れるため、必死で教えられたとおりの答えを自白するのみである。そこで「ほら見ろやっぱり反革命行為じゃないか」と拷問を受ける。もはや無間地獄である。こうして「私はベトナム軍と通じているスパイです」とか「CIAのエージェントです」「どこそこで破壊工作をしてました」などと自白させられては調書を取られ、拷問を受けた。CIAの単語すら知らないまま死んでいったCIAのスパイもいる。自白させられたあとは共犯者についても尋問される。知人や家族を同じ目に遭わせたくないから黙っていれば、さらにきつい拷問が待っていた。
S21で行われていたことは極秘中の極秘。政府も知らないことになっていた。どこまでも卑劣でおぞましい。看守は10代の少女も多く、命令されるまま収容者に対して拷問した。爪を剥ぎ、電流を流し、器具を使って骨を折った。そして秘密が漏れないよう最後は自分たちも殺された。ここにいるもの全てが、遅かれ早かれ殺された。
S21は1978年、ベトナム軍がプノンペンを占領したときについてきた新聞記者らに偶然発見されたが、生きて発見されたのは7人だけだったという。生存率実に0.04%である。これはナチスのユダヤ人強制収容所よりもずっと低い。
その施設は見るからに学校の校舎だった。
そのことがまず、悲しかった。

▲ S21(トゥールスレン)政治犯収容所跡の全容。元は高等学校の校舎である。
そんな教室の真ん中に金属製のベッドがみっつ並んでいる。フレームだけのそれは朽ち果て、床には茶色い染みが点々と、ときにべったりこびりついていた。拷問はあらゆる教室で行われていたようだ。ぼくは階段でフロアを移動し、廊下をつたってひとつひとつ部屋に入る。どの入り口のドアは開かれているのに、入る瞬間なにか身体にあたる感じがあった。また1分と居られないほど息苦しかった。飛び散った血痕は階段の壁にもみられた。

▲ 並んだ鉄のベッド。床に壁にこびりついて取れない血痕が

▲ 拷問が実行されていた部屋

▲ 階段の横の壁。ものすごい血しぶきが残る。上の他の写真もそうだけど、これらの血痕はわざと残してあるのか、それともなんど洗っても落とせないのだろうか?
おそらく簡単には死なせてもらえなかったのだろう。何か月も拷問を受けながらじわじわと死んでいくさまを、ここにいた人たちはどう耐えていたのか? ここの人たちは何を思いながら眠り、どんな気持ちで目を覚ましたのだろう?どんな死も死に変わりはないが、ここにはどんな死にも増す絶望がある。

▲ 囚人たちの独房。まともに横になって眠れないほど狭い。足かせが痛々しい
展示物もそこそこに、説明パネルもろくに読まず、だがすべての部屋を見て回った。ときおり廊下で立ち止まって呼吸を整えた。もともと廊下と校庭の間は腰までの高さの塀があるだけだったが、それ以外の空間は天井までびっしりと鉄条網がはられ、容易に外に出れないようになっていた。見学する人たちはみな押し黙り、ときおりボソっとひとり言のようにつぶやいていた。

▲ 拷問に使われた器具。後ろのパネルに使われ方のスケッチが。

▲ 吊り台。ここに囚人をぶら下げ拷問をした

▲ 外廊下と校庭の間には容赦なく鉄条網が張り巡らされている
昼の光を浴びて校庭はまぶしく、植えられたマンゴーやヤシの木が青々としている。そこに墓がずらりと並び死者が祀られていた。カメラを向けるとぼうっと発光した。露出をいくら下げてもシャッターが切れない。あきらめて少し付近を歩いてみた。離れの校舎との間に売店があり、そこで本が売られている。表紙を飾る大写しの顔写真。そばのテーブルにはなんと実物が座り、サインに応じていた。この収容所で生き残ったうちのひとりだった。

▲ かつてここに収容され、生き残ったうちの1人

▲ 校庭に並べられた墓。なんどもなんどもシャッターを押してようやく一枚とれた
そもそもポルポトはなんでこんなことをしたのか?
その世界観と戦術の類似性から、どうしても毛沢東がやった文化大革命が想起されてならない。あんのじょうポルポトは政権を取るまでの間、秘密裏になんどか北京に毛沢東を訪ね、そこで指示を仰いでいた形跡がある。ポルポトが自国民に対して行った「宗教と家族を消滅させ、通貨を廃止する」「都市と農村の格差をゼロにする」政策は、まさに毛沢東の思想そのものではなかったか。さらにいえば、毛沢東が中国でやりかけ、完遂できなかったことでもある。
革命は銃口から生まれる
と毛沢東は言った。だが
自国民に銃口を向ける国は長くない。






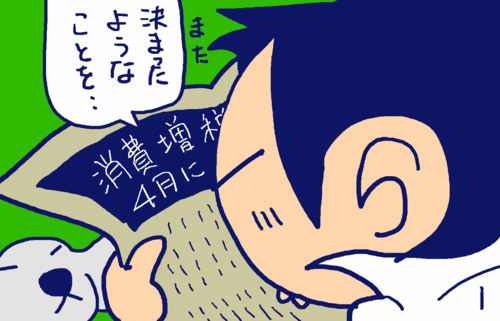

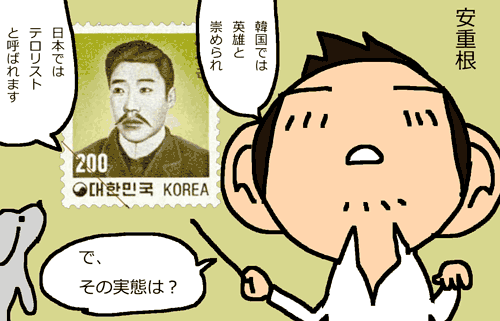
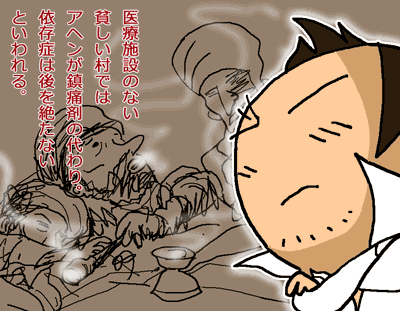
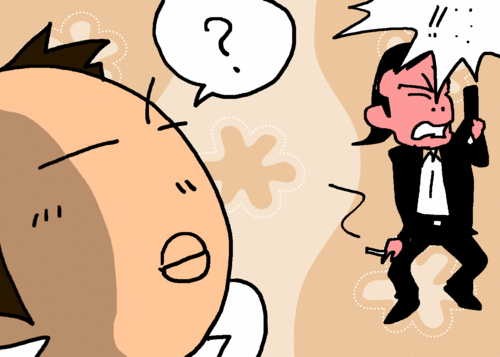

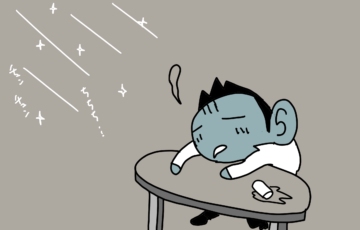
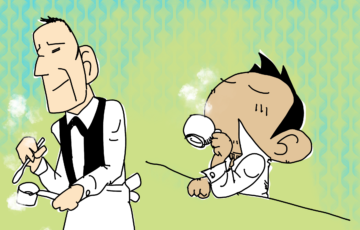
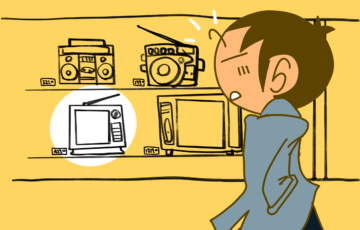
最近のコメント