ぼくの義理のおじいちゃんだった人は、リトアニア人だった。
はじめて会ったのは1985年の初夏、ちょうど今くらいの時期だ。
場所はロンドン。 当時のリトアニアはソ連領土に編入されていた。 ゆえに彼は英国で祖国独立運動に加わり、国外から支援活動をしていたのだった。
リトアニアはご存知のとおり北欧に位置していて、バルト海に面していることから、ラトビアとエストニアとともにバルト三国と称される。
日本とのつながりは、とりたて第二次大戦時に日本総領事館が国内に住むユダヤ人にビザを発行して国外に逃がしてやり、ナチスの迫害から守ったことくらいか。 それ以外にあまり目立った国際交流はない。
驚くべきは、このひとの壮烈な人生経験だ。
実にこの男、第一次大戦はロシア兵としてドイツ軍と戦い、第二次大戦はドイツ兵としてソ連軍と戦っている。 なんとも数奇な人生なのだ。
得難い人生だったかもしれないけど、しかし彼の望むところではなかった。 敵側の軍隊には、親戚や幼なじみもいたかもしれなかったからだ。 大国に挟まれた小国ならではの悲劇だ。 多くのヨーロッパの戦線では似たようなことがあったのだろう。
「ナチスが負けたのは仕方がない。 質のいい兵士や兵器はあったが、ロジスティクスがまずかった。 第一次大戦も同じ理由で負けた。 強すぎる軍隊は進撃が速いから、往々にして補給が間に合わなくなるものだ。 でも何もソ連にベルリンをとらせることはなかったんじゃないか。 ヒトラーは自殺し、統制がとれなくなった。 あまりにも負け方がひどすぎた」
そのような意味のことを彼は語り、
「その点、日本は強かった。ドイツが負けた後も、たった一国で全世界を相手に3ヶ月も戦ったのだから」と、加えた。
カムデン地区にある閑静な住宅街の一角に、彼ら老夫婦はつつましく暮らしていた。 奥さん(つまり義理のおばあちゃん)は、再婚したイギリス人である。 二人は勤務先だったハロッズデパートで知りあったのだそうだ。 2階の窓からのぞく新緑がキラキラと眩しかったのを覚えている。 滅多にないことだったが、その日は晴れていたのだろう。 おじいちゃんの目もとても澄んでいて、やはりキラキラしていた。 壁には、今の領土よりずっと広い、戦前のドイツ地図が貼られていた。
不思議なことに、ぼくの親戚や義理の親戚だった人には実に職業軍人が多い。 父親方の祖父は陸軍将校だったし、母親方は海軍だった。 けれどもふたつの大戦をはさんで、両方の軍を行き来していた経験はもちろん、ない。
義理のおじいちゃんにそのことを話すと、とてもうれしそうに「日本の軍人がいかに勇敢で規律正しかったか」を、なんども繰り返した。 ぼくがそれにおどろいていると、「今の日本は、お前たちにいったいなにを教えているんだ?」 と不思議がった。
おじいちゃんの話は興味深く、また示唆に富んでいた。 その割にはともに過ごす時間はあまりに少なく(イギリスとアイルランドの強行旅行途中だったのだ)、ぼくの22歳の頃の英語力では情報吸収に無理があった。
そこで「続きはまた来年」ということにし、早々にカムデンの家を離れたのだった。
別れ際、おじいちゃんは駅まで見送ってくれ、駅のホームで軽くハグし、電車に乗り込むぼくたちを腕全体を大きくゆっくり振って見送ってくれた。 なぜか軍人だった人はたいてい、そのような手の振り方をする。
だが結局のところ、その「続きの話」はなかった。
おじいちゃんは、ぼくたちが別れたあと、同じ年の冬に心臓発作が原因で亡くなってしまったのだ。
ひとは生まれる時代と親を選べない。 加えて場所も国も選べない。 20世紀元年にバルトの一角に生を受け、数奇な人生を送ることになった彼と、高度成長期の極東の島国に生まれたぼく。
折につけ、ぼくはその違いについて考える。
その違いは、あんがいとても些細なことなのではないか。
他人への思いやりは、そんな「相手が自分だったかもしれない」と想像することから生まれるのだとぼくは思う。
見聞を広めることで、ひとは謙虚なれるし、
経験を積むことで、より他人に優しくなれる。
そう思うことで、歳をとることに前向きになれる。 多くのものを失ってきたけれど、失うこともまた、前に進むための糧なのだ。
そんなふうにして、来週、ぼくはまたひとつ歳をとる。
それを成長というには、もう遅すぎるのだろうけれど、
もしかしたら、まだ間に合うかもしれない。
だって、まだまだやるべきことは、山ほどあるのだ。
■ わりと気になるもの
お台場に立つ原寸大(17m)の巨大ガンダム。ダイブ出来上がりましたね。 実際動いたらすごいだろうな、と。












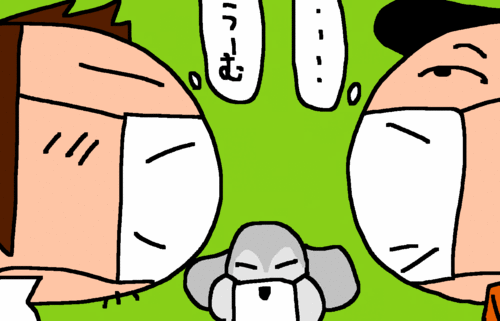

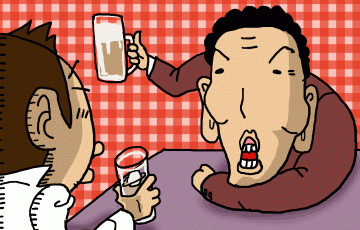

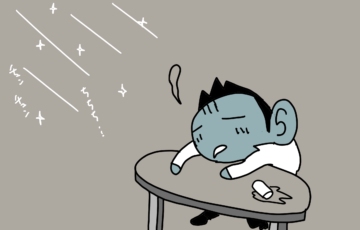
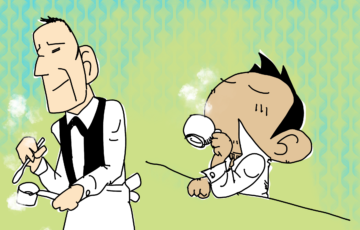
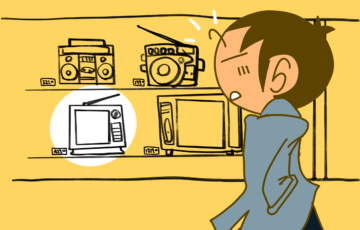
最近のコメント