「若者の活字離れがはげしい」などという。
ぼくはそのことに強烈な違和感を覚えるのだけど、繰り返し、そのようにいわれてきた。 さまざまな調査が行われ、もっともらしい裏付けが用意された。 が、その信憑性についての根拠は薄い。
メールやネットは基本的に活字メディアである。 活字離れどころか、むしろ活字依存度はますます高まっているんじゃないかと思う。
活字離れが顕著なのは、70年代からずっと「テレビ世代」といわれる40代〜50代のひとたちである。 彼らはネットについていけず、いまも暇なときはたいていテレビを見て過ごしている。
それでもマスコミや世間が騒ぐのは、本が売れなくなったからだ。 そして「本」というメディアが相対的に弱くなってきている実情を、「本を読まないからだ」といってみたり「日本人の教養が下がった」などと問題のすり替えをしているように思える。
「本が売れなくなった」というわりに、一年間に発刊される新刊本の種類は8万もある。 この数、1980年代のなんと4倍である。 いくらなんでも出し過ぎではないのか? ぼくは毎年300冊程度の本を買うが、ほとんどが「どっかで読んだことのある」ようなものばかりだ。 だいいち同じような性質の作者が、似たような内容の本を出し過ぎている。
新刊は出しまくっているのに、売上冊数は減っている。
2008年に日本で売れた本の冊数は7.5億冊。 90年代は9.1億も売れていたそうだから、なるほど「本を読まなくなった」と、つい言ってしまいそうになる。 でも言わない。 なぜならブックオフのようなリサイクル本の市場が伸びているからだ。 それから学生の図書館の利用冊数が90年代に比べ、2.5倍も増えているからだ。
本はあいかわらず読まれているのだ。
ネットやゲームがいかに流行ろうとも。
日本だけではない。『米国消費者レポート2009』によると、過去30年もの間、1人あたりの読書量は3倍になったと報告された。
先日の記事で「取次(とりつぎ)」のことに触れた。
このことで、多くの方から意見をもらった。 実際、取次会社のひとつに勤めるAさんからも厳しい意見をいただいた。
「我々がいなかったら、出版社はとうにつぶれていた」という。
そのとおりである。 取次なくして出版社はなかった。
取次の仕事は、書店への配本だけではない。
出版社にとって、銀行のような役割をも果たしている。
ふつう、商品というのは買い取りが基本である。
販売店は商品を自分のところで売れそうなぶんだけ現金で仕入れ、店先に並べて売る。 売れなかったものは不良在庫として処分するか、原価割れしてでもなんとか現金化する。 もっともそうならないよう商品の「目利き」がなくてはならない。 だからマーケティングが必要であり、利用者目線であろうとするのだ。
ところが書籍に関しては事情が異なる。
売れ残った商品を出版社に返品してもよいことになっているのだ。 もともとは弱小出版社が自分たちの本を売り込むために「あとで返本してもかまわないですから」と、とりあえず店に置かしてもらったことがきっかけである。 このシステムは成功し、大正時代には講談社がこれで黄金時代を迎えたといわれる。
世界でもまれに見る日本だけの『返本可能システム』。 それは画期的だったかもしれないが、さまざまな歪みをこの国にもたらした。
「返品可能」は、出版社、取次、書店それぞれに恩恵があるようにみえる。 どの業界も「売れそうにないものは仕入れない」のが基本で、だからこそ苦労だってあるのだ。 返品可能ならその必要はなくなる。
出版社から取次に売るときの卸値を、仮に70%とする。
このとき定価1000円の本を1万冊出版すれば、700円 x 1万冊 = 700万円もの現金が取次から出版社に支払われる。 まだ本屋でその本が売れるかどうかわからない時点でだ。 キャッシュフローに悩む小さな出版社にとって、この700万円がどれほどありがたいことか。 取次はこうして単なる仲介業者ではなく、ファイナンスの機能も持ちえるようになった。
もちろん、1万部発刊したところでぜんぶ売れるとは限らない。 半分しか売れず、売れ残りぶんが本屋から返本されてくる。 このとき出版社は取次に350万円返さなければならないが、このとき現金が足らなければどうするか?
また新刊本を作って納品するのである。
たとえば1600円のハードカバーを8千部、取次に買い取ってもらえれば、先ほどの計算式で890万円の現金化がなされる。 先の返本ぶんと相殺しても、500万円以上てもとに残る計算だ。 出版にかかる原価も払えるかもしれない。
出版社としては、まずはやれやれである。
しかしこれが無間地獄の始まりである。
本は売れなくなってきているのに、新刊が20年前の倍以上発刊される実情は、まさにここに起因する。
輪転機を回して本を作り、現金化することが目的になってしまう。
なんでもいいから取次に買ってもらえる本を作れ!となる。
これが出版社の陥穽となる。
出版社にとってのお客は「取次」である。
本を買ってくれる読者ではなく。
書店のほうもたまったもんじゃないだろう。
ある日、取次からどっさり本が届く。 1000冊くらい、まとめて届く。 バイトを雇い、せっせと新刊本を棚に並べる。 あるいは平台に重ねる。 売れるキャパを超えて送られてくればうんざりもするが、あとで返本すればいいから、とあきらめる。 場合によって箱から出さないまま倉庫に放り込んでおくこともある。 どうせ返すからだ。
返本された本はしばらく倉庫で眠ったあと、断裁される。 ムダに紙を使い、ムダにインクを使い、ムダにトラックで往復輸送され、ムダに断裁機を使い、ありがたがられもせず生涯を終える書籍たち。
かかわる者たちは今後いっさい「環境問題」を語るなと思う。
ところで日本の書籍流通は「再販売価格維持」ということになっている。 つまり、定価以外では売るなと指導されているのだ。
おかしいとは思わなかっただろうか?
ふつう、商品はメーカー小売希望価格として定価を表示するものの、実際いくらで売るかは小売店にまかせるものだ。 でなければ、独占禁止法に違反してしまうからである。 本来、自然淘汰に任せばつまらない商品は売れない。 価値は下がり価格が高ければ安くなる。 そこで、苦し紛れに作られたのがいわゆる「再販制度」である。
すでに書いたとおり、これらはまったく書籍流通の都合によるものだ。 返本することを前提とした流通システムだから、値段が途中で変わったりしないよう制度で保護したのだ。
読者不在の書籍流通。
それがこの国の、実態である。
テレビ局はマスコミにとって都合の悪いことは報道しないし、
出版社は取次や再販制度について都合の悪い本を出せない。
よって、なかなかぼくたちの知ることにはならない。
その意味で、DMZとしてのネットが必要なのだと思う。
電子書籍市場は、やはり生まれるべくして生まれる。
そのとき取次はその存在感を問われるが、出版社が生き残れるかどうかは、書き手と読み手のよき介在者として、どれだけ寄り添えるかどうかだと思う。
長い記事でしたが、最後まで読んでくれてありがとう。 しばらくしてまた読んでみてください。 きっと気付きがあるはずです。
![]() 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ
順位は落ちても応援してくださいね


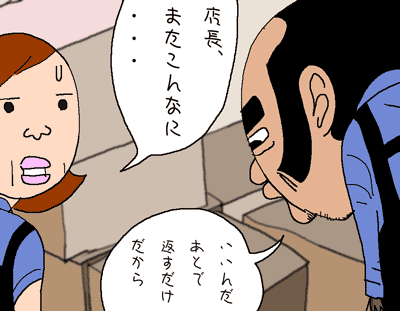











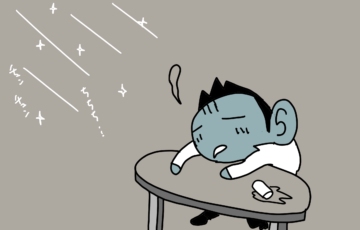
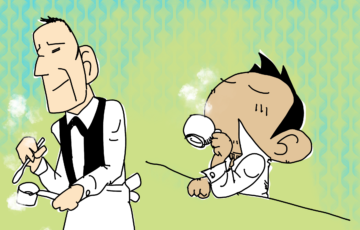
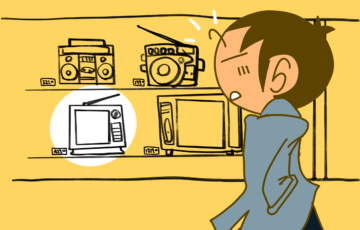
最近のコメント