
旅のハイライト、シェビ大砂丘へと向かう。
ガイド兼 運転手のヒシャムは、ジェフ・ゴールドブラム似のなかなかハンサム。砂漠へ向かうのに白シャツに細身のパンツに黒ジャケットを身をまとい、トヨタのランドクルーザーを操る。こちらはよれよれのシャツにカーゴパンツなのに。
古都フェズからシェビ大砂丘のあるメルズーガ村まで、距離にすれば約500km。朝8時に出発し、夕方には村に着く。だが間には4000m級のアトラス山脈が立ちはだかり、中腹の山道を抜けるためいくぶん多めに時間がかかった。

陽が傾き始めたころ、フロントガラス越しに砂丘を認め一気にボルテージが上がる。砂丘は思っていたよりずっと高く、砂の色が濃い。20年前にチェニジアで体験した砂丘よりずっとスケールが大きい気がした。
メルズーガに到着し、さっそくラクダに乗り換えれば、そこはもうサハラ砂漠。ホテルの敷地内にひたひたと砂の波が押しよせてきている。大きな荷物を施設に預け、そこから大砂丘の真ん中に設置された備え付けのテントへと向かう。そこが今夜の宿である。

傾いた陽があたりの砂丘に影を作り、サハラの風が砂紋を作る。ラクダはもともと乗り物には適さないのではないか。胴回りは思いのほか広く、またがった股間がなかなか安定しない。ラクダもぼくにまたがられてなんだか迷惑そうである。時おり、ぶひひひひと鳴く。
ラクダの首根に固定されたハンドルから手を離し、あたりの写真を取ろうと身体をねじると、とたんにバランスを失い、落下しそうになる。あわてて態勢を整えながら、馬から落ちれば落馬だけど、ラクダの場合は落駝(らくだ)かな? そのまんまじゃないか、などとどうでもいいことを考えていた。

ザクッ、ザクッとリズミカルな足音以外、まったく音がしない。ときおり風が空気を切る音がする。きっと砂が音を吸いとってしまうのであろう。しんしんと積もる雪のように。

ラクダはぼくらを乗せ、砂の丘を超え、砂の谷を降りる。ヒジャブ(スカーフのこと)を頭に巻いていたが、砂塵が風にのって頬にたたきつけてくるので、目を残して顔全体をそれで覆った。動物の背に揺られているとつい、口笛を吹きたくなる。歌を歌いたくなる。くるぶしの内側に直接当たるラクダの横腹があたたかく、毛皮がすべすべして気持ちがいい。ぎゅっと両脚ではさめば不思議な一体感があった。まるでケンタウロスになった気分である。

そのようにしながら美しい砂紋を眺め、どこまでも続く砂丘を照らす夕日にあたりながら、ラクダの隊列はテントに到着する。もうすぐ日が暮れるだろう。ラクダを降り、近くの砂丘を駆け上り、その稜線のひとつに腰を下ろして洛陽を眺めた。

陽が完全に沈んでしまうと、いつしか星空が天空を覆っていた。星はみずみずしく瞬き、人工衛星が一定の速度で移動しているのが見えた。
ぼくは砂丘の斜面に横になり、天空を見上げる。やりたかったことのひとつである。サハラ砂漠に大の字になって、星空を眺める。
テント付近から賑やかな音楽が聞こえてきた。
ラクダ使いが打楽器で演奏をし始めたらしい。そのうち「おーい、ジャパン!こっちきて踊れ〜」という声が聞こえてきたが、無視をした。
やがて音がやみ、テント周辺の灯りも消えた。
砂漠の表面は冷たく、背中がしびれるように冷たくなってくる。
それでもかまわず星空を眺め続けた。
今見えている星は今はもうなくなっているかもしれない。何億光年も離れていれば、地球にあたる光があちらに届くには何億年も先のことである。ぼくたちは空は広いと思う。だが空の広さなんて宇宙の深さに比べれば砂の粒ほどに小さい。まして自分という存在なんて、砂粒ほどにもならない。



そんなことを考えながらいつまでも星空を眺めていた。
自分の存在が小さく遠のいていく意識は、なかなか心地よいものがある。人に宗教が必要なのは、だからなのだと思う。
今回の移動ルート










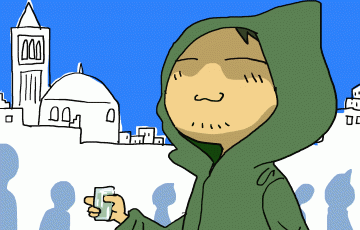

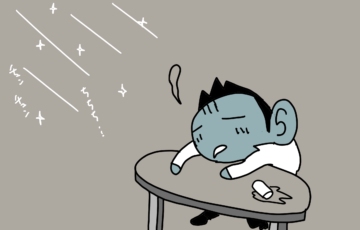
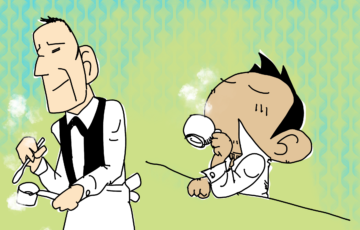
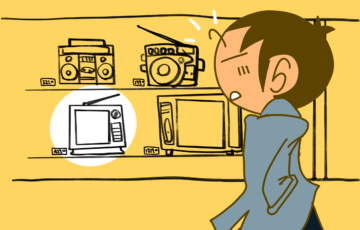
最近のコメント