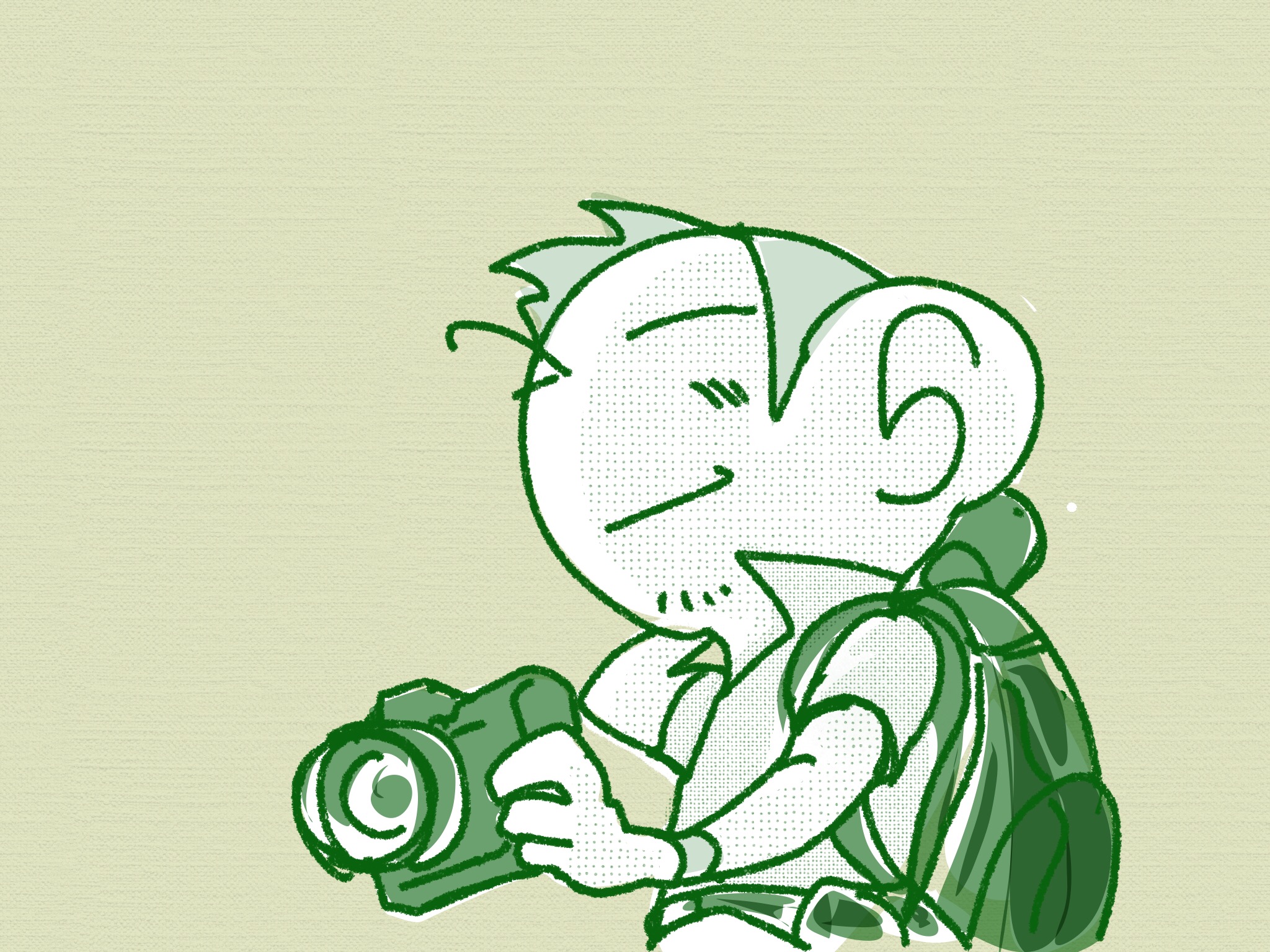
カサブランカ空港に到着したのは、自宅を出てからゆうに24時間を越えていた。そこから列車で街中まで行き、メクネスの中央駅につくまでにさらに4時間、タクシーでカスバの入り口まで連れて行ってもらい、そこからは歩いて予約してあったリャドへ向かう。
これがなかなか見つからない。
紙に書いた住所を見せ、場所を聞くのだけど、教えられた場所にリャドはなく、もときた道に戻ってしまう。あらためて違う人に道を聞くが、同じことが繰り返される。モロッコ人は「知らない」という言葉を使わない。胸をはり「それならそこを右に入って、次を左にまっすぐだよ」などと自信たっぷりに、間違う。

お願いだから、知らないならそう言ってほしい。とぼくは懇願する。別の人に聞けばいいだけだから。そのうち「こっちだよ、ついておいで」と、ものすごいスピードで人混みをかき分け、ずんずんと進むおじさん。見失わないよう、ついていくのがやっとである。
ようやくたどり着いたのは、さらに半時間を過ぎたころ。案内をしてくれたおじさんは「ガイド料を」と手で示し、そのボールペンももらえないかな?と哀願してきた。とりあえずチップを渡し、ペンはダメだと答える。おじさんはあっさりと、ああそうですかと去っていく。ボンボヤージュ! なんとなく昔習った社会科の先生の面影があった。

メクネスのカスバはそれほど大きくないので、それほどまよったりしなかった。と誰かのブログにそう書いてあったが、ぼくには通用しなかったようだ。たっぷり機内で移動時間を過ごしたが、あまり寝たような気がしない。丸2日起きていたようなだるさのなか、リャドの主人に教えられたレストランでサラダとタジン鍋、羊のケフテを食べ、宿に戻ってそのまま気を失うように眠ってしまった。

まどろみの中、風の音で1度目を覚まし、消し忘れた灯りをオフにした。
それから夜明け前にベッドを離れ、リャドのテラスで朝焼けのメクネスの街を眺めて過ごした。モスクのミナレットは一晩中ライトを灯し続け、人々の心に迷いのないあかりを灯していた。


このころになってようやく、旅にでたんだという実感がふつふつをこみ上げてきた。最後に来たモロッコは1984年の7月のこと。あれから当時の年齢の倍以上の時が流れ、ぼくはどこにでもいるおじさんのひとりになった。
バックパックを担いでもそれは変わらないが、そう思うのは自分だけなのも知っている。メクネスの街にゴミ箱はなく、かまわず人々に捨てられたごみが風に舞っていた。












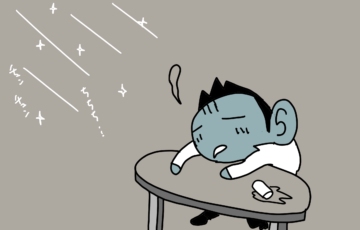
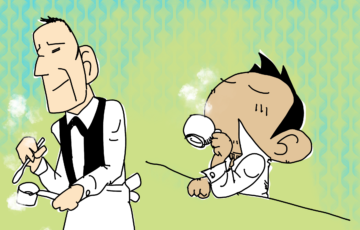
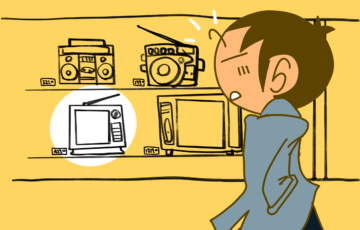
最近のコメント