青空を見上げる。
空に浮かぶ雲が、動物など何か別のものに見えたりすることが、あなたにもあると思う。実を言えば、そういった偶然なにか別なものに見えるラインや形を、飽きずにじっと見てしまうクセがぼくにはある。
あるいは木と木のあいだ、葉と葉の間。それらの輪郭によって切り取られた背景、たとえばその向こうにある青空に焦点を合わす。風が吹き、枝が揺れるたびに、動き、明滅する。めまぐるしく変わる。この瞬間、次の瞬間に、変貌する形態を飽きずに凝視してしまう。好きとかそういうんじゃない、ただのクセである。
40年も昔、小学校の写生の時間。
担任の先生はすこし不思議そうにぼくの絵を覗きこむ。「どうして木の中に星があるの?」と。その時のぼくの描いた絵には、一本の大きな木の枝や葉の部分に無数の星が描かれていたのだ。真昼の丘の上で、キラキラと大小さまざまな星を描く子供。「昼でも星が見える」のは目が良すぎるモンゴル人であり、たぶんぼくはただの変な子供だったのだ。当人にしてみれば、みんなそうだと思っていたのだけれど。
むかし読んだ司馬遼太郎のエッセイか何かで「妖精を見る眼」というのがあった。古来、ケルトに縁のある文人や詩人には「妖精を見る眼」を持った人が少なくない。たとえば『シャーロック・ホームズ』を書いたコナン・ドイル。『ふしぎの国のアリス』を書いたルイス・キャロルなども、そんなひとであると。そんな人たちがかく「だまし絵」。輪郭との間に見える別なフォルムから生まれる生物を、アイルランドでは妖精と呼んでいる。といった内容。それを読みながら、自分にも妖精を見る眼があるかもしれない、などとうぬぼれた記憶がある。すこし違うような気が今ではするが。
思うのだけど、形の裏(というのかな?)を見る趣向は特殊な才能でも何でもない。それはただのクセである。ぼくが下手くそなりにデッサンをするとき、物の形を捉えるために重心の位置や対照、線と線の比率などを見ていたりする。でないと構図のバランスを崩すし、あえて崩すとき、元に戻れなくなってしまうからだ。ぼくはそのことを誰かに教わったわけではない。ただ何となくそうかな、と思っているだけだ。
そのような物と物の「間」を見てしまう子供からのクセ。大人になってからは、物事のウラを見るクセに変化した。いや退化した。たとえばある事件が起きるとする。ぼくは事件そのものより、その背景ばかりにピントがいく。「ウラ読み」というと姑息な気がするが、まあそんなものかもしれない。こんなふうにものを書いていても、知らず、たまにその傾向が出るようだ。
見えるはずのないものが見えるとき、焦点がいささかずれていることが多い。あれは霊だと思っていたが、あんがい「アイルランドの妖精」だったのかもしれない。視覚だけでない現象については、おいおい考えるとして。







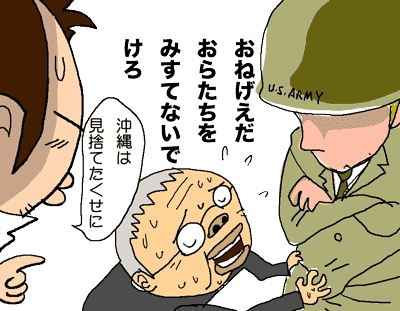
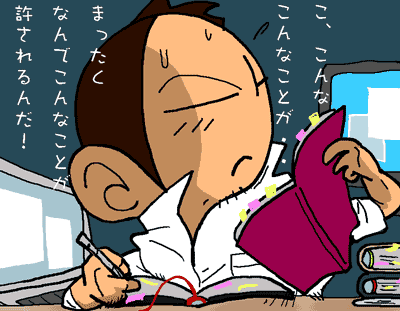


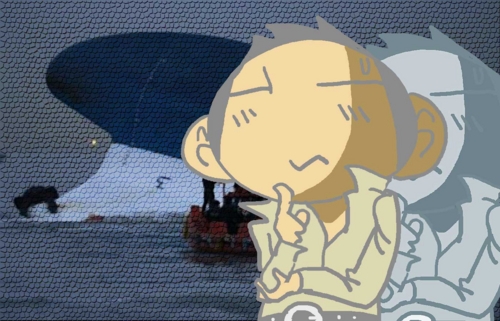

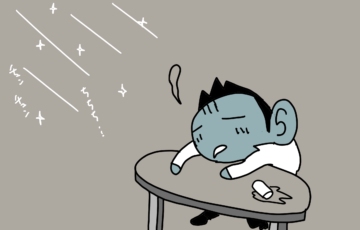
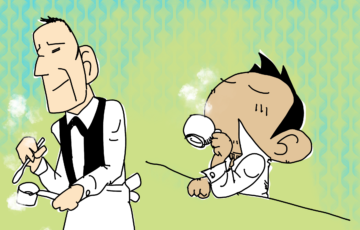
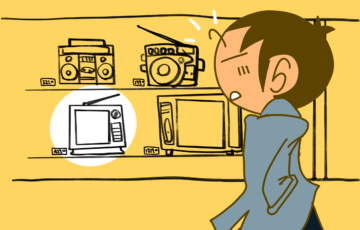
最近のコメント