なんどかここにも書いたけど、ぼくは人間を観察するのが好きだ。そのうごきを、たたずまいを眺め、ときにその人間の暮らしぶりのようなものを想像する。知っている人より知らない人の、たまたま見かけただけの、そんな人間たちが観察するのにふさわしい。
ただ女性をじろじろ見るのはあまりよろしくないので、もっぱら男を、いやこれはこれで問題があるのだけど、とくにおじさんを眺めたりする。ぼくと同年輩の、いやもう少し年配のおじさん。ちょっとくたびれて疲れていそうなおじさんだ。はた目にはぱっとしないのだけど、実はすごい経歴と実力をもっていたりするのだ、きっと。みじんもないかもしれないが。
人間観察をしているとき、ぼくはたいてい疲れている。自分や周辺に立ちふさがる問題にばかり夢中で、心によゆうがない。よゆうがないから、そこによゆうを生もうとするなにかしら防衛本能のようなものかもしれないなと思う。
今回は、そのようにして眺めたおじさんのスケッチに、もしかしたらその心に浮かんでいるかもしれない「人生の名言」を添えてみました。ほら、どこにでもあるちょっと間の抜けた顔が、なんだか哲学者に見えたりしませんか?しませんね。すみません。
ではさっそく
サン・テグジュペリといえば『星の王子さま』の著者で有名ですが、個人的には『人間の土地』が大好きでいまでもたまに読み返したりします。この一文は『戦う操縦士』という自叙伝のなかにありました。「徐々に生まれる」いい言葉ですね。学び、鍛え、発見し、反省する。そのたびにおじさんが生まれるのです。おじさんがうじゃうじゃと生まれ、ていうか、わく。ああ、こわい。
合衆国教育長管などを歴任した政治家であり哲学者のベネット氏の言葉。「なりたいもの」になれるよう努力しても、「なりたくないもの」にならないよう努力することは案外みおとしがちです。毎日ぼんやり暮らし、気がついたら「こんなはずじゃなかった」てなことに!そういうことにならないよう、日々振り返る必要があるという戒めです。そう、突然ではないのです。このたるんだお腹だって、禿げあがった頭にしたって。

生まれ生まれ生まれ 生まれて生の始めに暗く、 死に死に死に死んで 生の終わりに冥し
ご存じ空海の言葉です。人間はなんど生死を繰り返してもまた生きてまた死ぬ。でもなぜ生きて、なぜ死ぬのかやっぱりわからないという輪廻の輪を表した一節。光も見えず、闇も見えず。そんな人間のはかない業のようなものを感じます。おじさんはいつの時代もおじさん。そしてやっぱりおじさんなのですね。
良寛の死ぬ一週間前に詠んだといわれる歌です。こういう「散る」という響きがマゾ的に好きなのがぼく。いや日本人なのかもしれません。病に伏せ、庭のもみじが散っていくようすを、おもてもうらも隠さず見せながら死んでゆく生きざまをあらわしています。おもてばかりを見せながら死ぬことはできないのが人間。おじさんなんかとくにそうですね。ウラばっかりのおじさんも、ごくたまにいますが。
あなたのまわりのおじさん。
臭いだの汚いだのといわず、
たまにはいたわってあげてほしい。
よくみるとほら、こんなにも愛おしい。
■ 爆弾低気圧による大雪










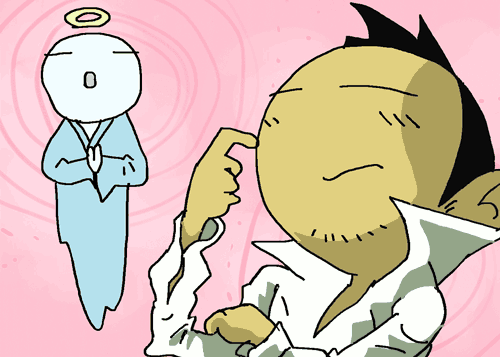



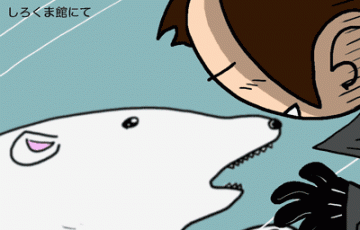


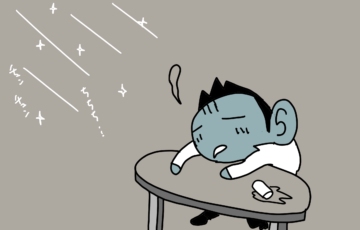
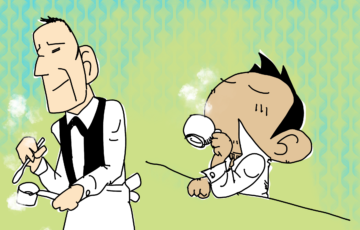
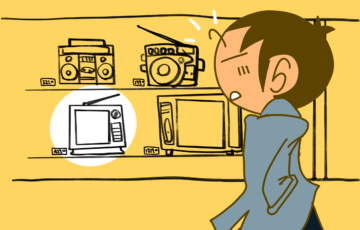
最近のコメント