秋がひといきにやってくるこんな時期になれば、さすがにぼくもいろいろ考えてみる。はやい話が少しナーバスになる。自分という人間がたいしたことのない存在に思え、代わりに周りの人間たちがたいそうに思えてくる。
窓から差す光も細く短い。開いてもいないのにどこからか風がやってきて机の上の植物を、ついでに思いを揺らす。
泣いてもわめいても時は流れ、そのうつろいについていけないことがある。朝目が覚めて自分が49であることにおどろき、戻れない多くの場所に思いを馳せては、取り返しのつかないことをしてしまったような気になる。
やがて冬になればあきらめもつくのだろうが、まだ端境のふちに立ちつくせるぶんよけいたちが悪い。
そんなとき、ふいに蜂蜜色に染まるまっすぐな一本の並木道を思う。あれは南フランスのアヴィニョンへ向かう道だったか。走っている車はどれも金色の液体を振りかけられたかのようで、バックミラー越しに目のあったあの中年男はもう二度と会うこともないしそもそも会ってすらいないが、いまどこで何をやっているのだろうかと並木道とともに思い出す。あれもまた戻れない多くの場所のひとつ。目が覚めたとたん、そんなことをまどろみの中に浮かばせるのが秋という魔法だ。意識がまともに戻る直前に、後ろへと通りすぎ去る小さな公園でペタングをやる男たちのシルエットが右目のふちに少しだけ見えた。カセットテープの小泉今日子が少しだけ鳴った。
開いた雑誌のページに視線を落とすが文字が頭に入らない。コーヒーは飲まれず冷める。ティッシュに手を伸ばし鼻をかみ、ゴミ箱までやっとの思いで腰を上げる。ひとつひとつが緩慢で、誰かをおぶっているように身体が重い。もう3年以上風邪をひいていないが、熱があるのかもしれない。脳が無駄にはたらき、ふだん通うことのない部分に血がまわったのだろう。だとすれば将来の糧のひとつでも思いつけばいいものを、意識はただ空をさまよい、忸怩たるなにかといっしょに舞い落ちてくるだけだ。
人は動きたくないぶん、人を動かす。
宅配ピザを頼み、ただ腹を満たすだけの夕食をとる。ピザの縁をちぎって犬にやるが、一度くわえてから床にぽとりと落とす。ぼくを見上げ「チーズのついているほう」と目としっぽで要求する。外が暗くなってからそれほど時間が経っていないが、もう何もかもしたくない。だがマックブックを開き、布巾をかたく絞るようにこれを打った。もう数滴残っているが読む方もたまったものじゃないだろうから、この辺で。
なおきんのつぶやきでした。
みなさん、良い週末を。





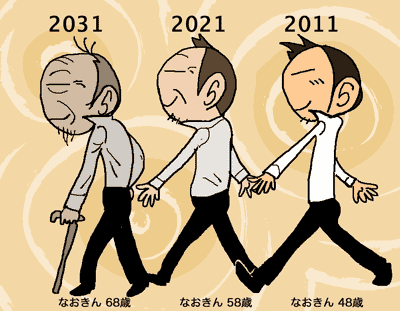
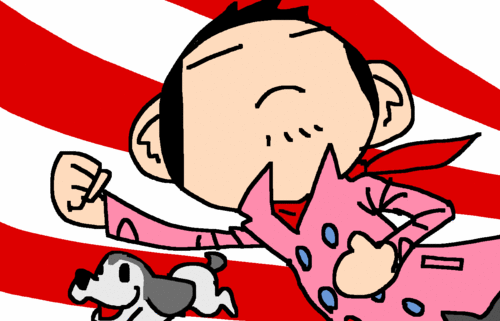







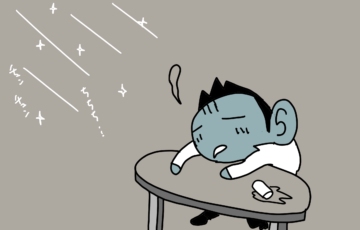
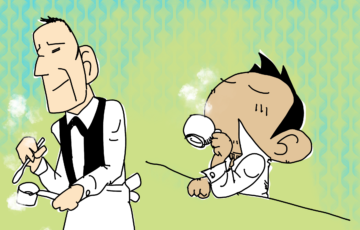
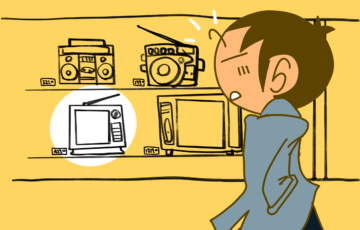
最近のコメント