アゼルバイジャンの首都、バクーに到着したのはまだ夜が明けていない午前5時。ターンテーブルで自分の荷物を待つ必要のないぼくは、一番で到着ロビーを抜けた。数十人の人たちが一斉にこちらを見て、自分の待つべき相手でないことを知ると、一斉に無視した。
無視をしないのは客待ちのタクシーの運ちゃんだけである。しかもぼったくりがうまい輩ほど、積極的に声をかけてくる。それも両替カウンターの前で。
ATMで100マナト(約一万円)ほど下ろし、さっそくタクシーの値段交渉。ほどなく25マナトで決まった。相場は知らない。最初相手が50マナトと言ってきたので、半額に下げさせただけのことである。
産油国だけあってバクーの街は明るい。
節電せずともおとがめなしなのだろう。ガソリンスタンドに表示されている看板をみて、1リッター50〜70円が相場ということを知る。

▲ 夜が明けたばかりのカスピ海
ホテルはなかなか見つからなかった。運転手は車を停め、荷物を持って城壁内をぼくと一緒に歩き回る。「このへんなんだけどな・・」と運転手はいう。だが見つからない。2晩、ろくに眠っていないぼくの疲れた目に、街はあまりに美しかった。
ホテルは見つからなかったが構わず、ぼくは運転手と別れた。そうして明けたばかりの旧市街をホテルを探しながら散策することにした。とはいえ、カスバのように入り組んだ階段ばかりの旧市街。結局ケータイでホテルに電話をし、自分がいるところまで迎えにきてもらうことにした。のんびりした街である。朝の6時に客から電話があれば、歩いて迎えにきてくれるのだから。
ホテルは「これじゃ見つからないよな」という場所にあった。
チェックインは午後2時、ということだが、7時前には部屋でシャワーを浴び、しっかり朝食までごちそうになった。いい人たちである。「日本人かい!はじめて見たよ。中国人なら何度もあるけど」掃除のおばさんはものすごいブロークン英語で話しかけてきた。世界にはまだそんな場所があるのだ。
カスピ海からの風は強い。
「バクーは風の町」どこかにそう書いてあったとおりだ。だからか、帽子をかぶる人をほとんど見かけない。ヅラだって飛ばされる。禿げている人は隠せない。目に砂が入り、開けていられないほどである。
カスピ海の沿岸まで歩いていき、そこに停まっていたタクシーを捕まえ、「ヤナー・ダグへ行ってくれ」と言った。そこでは岩の間から天然ガスが吹き出し、岩が燃えているのが見られると聞いたのだ。アゼルバイジャンの先祖はゾロアスター教(拝火教)を信奉していたが、燃えるガス(天然ガス)や燃える油(石油)が、これの名残なのかもしれない。こんなに価値が生まれるとは、当時誰も想像していなかっただろうけど。
ホイ来た、と郊外へ走り出すタクシー。
だが60歳前後と思われるその運転手は、正確なその場所を知らなかった。他のタクシー運転手や、ガソリンスタンド、スピード違反のきっぷをきっている警官に聞きながら、同じ道を何度も行ったり来たりした。そのうち「燃える岩なんてあるわけない」「あったのは、ずっと昔のことだ」とまで言い出す。ぼくはiPhoneをとりだし、検索し、Yanar Daghの写真を運転手の鼻先につきつけた。よくみろ、ここだ。
すったもんだしながらようやくたどり着いたのは、1時間以上も経ったあとだった。なにしろガイドも、ガイドブックも何もない。地図すらない。運転手は頼りにならない。頼りになるのは、iPhoneのナビだけであった。
「おいらシンっていうんだ」
運転手は欠けた前歯でニッと笑う。帰り道にいきなりの自己紹介。はじめて燃える岩を見て、ホッとしたのだろう。さっきから会話はすべてものすごいブロークンな英語と、ロシア語だけである。途中から雨が振り出し、やがて土砂降りになった。「今月最初の雨だ」とシンはいう。道路はいつの間にか大渋滞になっていた。
「中国人か?」ときかれ「日本人だ」と答える。「いくつだ?」と聞かれ「49だ」と答える。シンは驚くそぶりを見せ「うそだろ?」といい、「俺の方が若い、48だ」と付け足す。うそだろ!と言いたいのはこっちのほうだ。ともあれ、会話らしい会話がようやく始まった。12年前、ロシア領の北コーカサスからやってきたのだという。あっちはひどい生活だったよ。と首をふりながらシンは回顧する。「なるほど」と言いながら、ぼくはそのまま眠ってしまったようだ。

▲ 巨大な「博多名物ひよこ饅頭」にもみえる建ったばかりの高層ビル。モチーフは炎。「夜になればわかるよ」と通りすがりのおじさんに言われた

▲ 雨のカスピ海
寝ぼけたまま街の中心でタクシーを降りる。
ざあざあ降る雨に打たれて目が覚める。とりあえずは雨宿りである。すぐそばにレストランの文字を見つけ、半地下の階段をくだったそこは、自家製ビールを売るパブであった。
バクースペシャルと書かれたビールは旨い。チェコのピルゼンで飲んだビールと同じ味がした。メニューを見て、ヴィーナー・シュニッツェル(ウイーン風仔牛のカツレツ)も注文した。レモンを絞って食べれば、もうここがどこなのか一瞬わからなくなるほど美味しかった。
腹ごなしに、街に出る。
雨は相変わらずふり続いていたが、傘もささずフラフラさまよう。周りの人たちもほとんど傘をさしていない。そういうものなのだ。バクーはどこも清潔で、とてもきれいな街だ。通りを変えれば、違う顔を見せる。ブロックを越えれば違う国のようにも思える。バルセロナのようであり、パリのようであり、カサブランカのようであり、イスタンブールのようである。これは楽しい。夢中になって歩くうちに、日が落ち、今度は夜景が広がった。
これほど散歩をして気持ちのいい町もないだろうにと思う。
バクーはとてもドラマチックなのだ。

▲ おっぱいがいっぱい・・じゃなくこれはハマム(銭湯)の屋根です

▲ ありえないくらい近代的なメトロの入口、よくみると屋根が魔法の絨毯だ
▲ モスク。中からコーランが聞こえてきた。実はモスリムたちは肩身が狭いのだ

▲ 恋人たちはこっちの噴水を見てうっとりする。カスピ海の水が吹き上げる。まるでレマン湖のそれだが、バクーのそれは以下にも石油バブルっぽい気がする
そして、「夜になればわかる」の意味が、わかった。
これだった。

▲ ビルの壁が巨大なイルミネーションに!炎がメラメラと動いていた。
アゼルバイジャンはオイルマネーのおかげであるところには金がある。ないところにはない超格差社会である。明るいバクーの街を歩いているとそんな風には見えないが、ぼくはシンの言葉を思い出していた。
俺の給料がいくらだか知っているか?たった500マナト(約5万円)だ。いつか日本にいってみたいが、今世紀中はたぶん無理だ。
ーー





























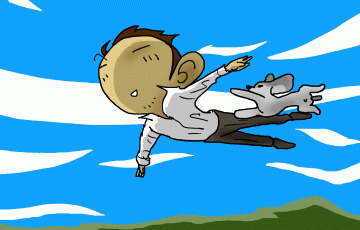




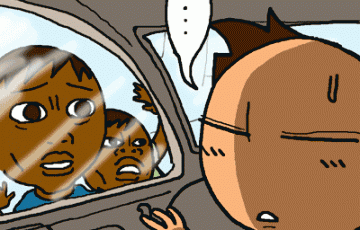

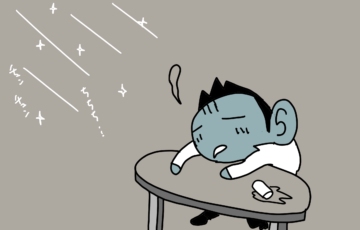
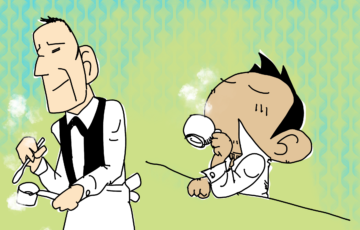
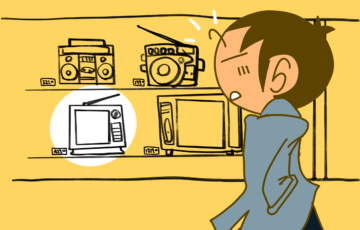
最近のコメント