ぼくたちは漆黒の闇の中にいる。
足下に懐中電灯をあて、おそるおそる前に進む。 ごつごつした石灰岩を靴底に感じ、ぽたりと落ちる水滴を首筋に感じる。 ヘルメットが岩肌にあたり、ガコッという大きな音にドキリとする。
来るんじゃなかった、と思う。
少なくても引き返すチャンスはあったのだ。
「霊感は強いほうですか?」 とガイドの上原さんからそう訊かれたとき、ぼくは意地を張らず「はい」とだけ答えていればよかったのだ。 そうすればいまもこの得難い恐怖を感じることなく過ごせていたのに。
太平洋戦争末期の1945年4月1日、ついにアメリカ軍は沖縄本島に上陸を開始した。 上陸前から執拗な爆撃や艦砲射撃をくり返し、地上にあるほとんどのものを破壊し、凄まじい砲撃は山の形すら変えた。 当時50万人都市だった沖縄はこうして壊滅した。 日本本土からの補給はとだえ、ただでさえ不足していた医療、食料、弾薬などの物資は地上でさらに失われた。 その頃の日本にはもうまともに戦える軍艦も飛行機もなかったが、あったとしても、やがて日本本土に攻め入るアメリカ軍との決戦のために大事に保管されていた。
上陸したアメリカ兵は、地上で動くあらゆるものを撃った。
空からは戦闘機がおもしろ半分で逃げまとう人々を機関砲で撃ち殺した。 まるで狩りでもしているかのように。 人々は生き残りたければは地下に潜り、米兵に見つからないよう息を止めているしかなかった。 沖縄には人の手による掘削壕のほか、自然がこしらえた洞窟がいくつもあった。 将兵も、住民も、病院も、なにもかもがそこに移された。
ぼくがいる洞窟は、かつて陸軍病院の分室として使われていた場所だった。

▲ 当時の南風原陸軍病院。丘の中腹にトンネルを掘って作られていた。
「負傷した兵の足を切り落とすとき、のこぎりはあっても麻酔がありませんでした」 と、ガイドの上原さんはおごそかに言う。 有名な”ひめゆり部隊”の女学生たちもここで軍医や看護師達とともに働いていたのだ。

▲ ひめゆり部隊の慰霊碑
糸数アブチラガマ洞窟の中は真っ暗である。
ただの一筋の光もない。 手にした懐中電灯のみが頼りだ。 闇には質量が感じられ、空気はひんやりとしている。 それが気温によるものだけではないことはわかる。 肩にぽたり、鼻先にぽたり、天井から地下水滴が落ちてくる。 数時間もいればびっしょりになるはずだ。
闇が怖いのではない。 存在するはずのない人々の、ひたひたと忍び寄る気配が怖いのだ。 ガイドの上原さんはそのことを知ってか知らずか「ここは破傷風患者たちがいた場所」「あそこは脳症患者だった」などと懐中電灯をそこへむける。 そこに丸く切り取られた光の輪ができる。
「いる」とぼくは思う。
普段ならそういう場所では「感覚」を閉じることでそれを避けることができた。 でもここでは圧倒的な数と闇が、閉じたはずの隙間を狙って「感覚」にわり込もうとする。 ぼくは息を止め、心の中で念仏を唱えていた。
▲ 洞窟の中の病院のベッドのようす(南風原文化センター)
▲ ぼくもちょっと横になってみた
▲ 洞窟内での手術の様子
洞窟の長さは270m、そこに負傷兵、住民、看護師、軍医など600人がひしめいていたという。
「本当は1000人いたともいわれます。そのほとんどは亡くなられましたが」と上原さんは言い、この洞窟で日本兵がいかに住民に冷たく、かつ自分勝手だったかをとうとうと説明する。 話の内容は正確かもしれないが、個人的な主観も強かった。 「弱者を置き去りにした」「沖縄を本土決戦のために犠牲にした」と何度も繰り返した。 それでも生きている人間の声がいまはありがたかった。 話をやめてほしくなかった。 暗闇も怖かったが静寂も恐ろしかったのだ。
だのに上原さんは、懐中電灯の明かりを消し「冥福を祈って1分間黙とうを捧げましょう」という。 こうして一分間、ぼくたちは目を閉じ、口を閉じた。 暗闇の中で手を合わせ、無我夢中で祈る。 目を閉じていたほうがむしろ明るかった。
「この洞窟の入り口ではシャッターが押せなくなる」となにかの本に書いてあった。 まさかとは思ったが、ぼくのカメラもシャッターが押せなくなっていた。 それどころか勝手に録画が始まっていた。 慌てたぼくは苦労してバッテリーを引き抜き、停止させた。

▲ 洞窟に入って入り口のほうを写す。そのとき、なにかがぼくにぶつかった
「こちらを見てください」と上原さんはそこに懐中電灯をあてる。 人の靴跡が見えた。 「観光客のものです」 といい、光を靴先部分にずらし「ではこれはなんですか?」とぼくに質問した。
光が照らされたそこをみると、砕けた人骨があった。 ここに入る観光客は、知らず無縁仏の骨を踏んでいたのだ。
出口近くに来ると井戸が見えた。 地下水が溜まるようこしらえたという。 この水は洞窟に潜む人たちにとって生きる望みだったはずだ。 だのにアメリカ兵はこの先の穴から洞窟内めがけて火炎放射器をぶっぱなし、出口付近に潜んでいた人々を燃やした。 それでも奥に人が生きているとわかると、こんどは長い砲塔を洞窟の穴に突っ込んで、弾を撃ち込んだ。 砲弾は火の玉となり付近にあったドラム缶に当たって爆発した。 ドラム缶は爆風でふっとび、一部が天井にべったりと張り付いていた。 おそらく人の肉片も同じ運命だったことだろう。

▲ そうとうな衝撃で張り付いたと思われるドラム缶片、それにしてもこの写真!
とにかく外へ出たくて、出口へ駆け上っていこうとしたとき、
「なぜ洞窟を出れるかわかりますか?」と不意に上原さんは言う。
「外が安全だということを私たちは知っているからです」 でも、と上原さんは続ける。 「ここにいた人たちはそうすることができませんでした。 出れば殺されることを知っていたからです。」
この洞窟で生き残った人々が外に出たのは、終戦後1ヶ月経ったあとだったという。 しばらくは戦争が終わったことすら知らなかったか信じなかった。 そうして暗闇の中でひっそり息を潜めていたのだ。多くの死体と一緒に。
せつないほどに美しい沖縄の海と大地。
闇が深いほどに、まばゆく輝く。
犠牲者のご冥福を心よりお祈りいたします。








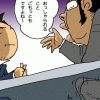






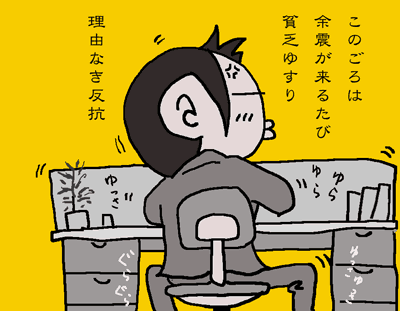



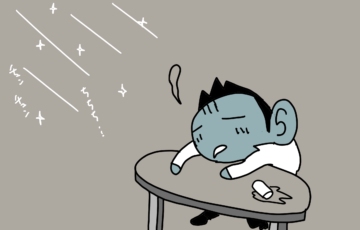
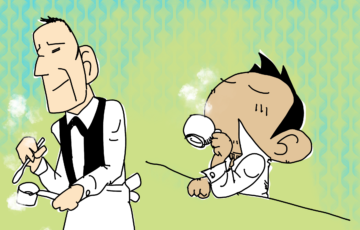
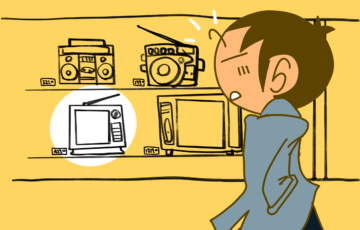
最近のコメント