いったいどのくらいパスワードをタイプしているのだろう?
会社勤めの人ならば、やれイントラネットだの、個人情報だのと
たぶん5つや6つじゃないはずだ。
しかも、
数字とアルファベットを組み合わせて、とか
パスワードの期限が切れたので新しいパスワードを作れ、
しかも、5世代前までは同じパスワードが使えません
などと、条件や注文が多い。
パスワードを忘れ、使えなくなったサービスもあるし、
パスワードを忘れたことすら忘れてしまったアカウントもある。
長いこと待たされてサービスセンターに電話をかけて再発行してもらいながら、なかなかしんどい世の中になったものだと思う。
バブル時期のころなんてせいぜい
キャッシュカードの暗証番号くらいだった。
それすら数字4桁のみ。 ああ、なんて牧歌的。
むかし、まだぼくが20代後半のころ、
取引先に社長の秘書をしている女の子がいた。
なかなかかわいらしい日本人の子だったのだけど、
いま思えば、ちょっと不思議ちゃんだったような気がする。
彼女はコンピュータソフトの調子が悪くなると、
電話をかけては ぼくを呼び、
他に用事を作っては、しかたなくそこへ車で向かった。
片道220kmも離れた街にそのオフィスはあったから、
呼ばれたら直ちにというわけにもいかないけれど、
大口の取引先だったしで、ほおっておくわけにもいかない。
彼女の席のとなりにイスを持ってきて座り、
作業をしようと端末の画面をこちらに向けるのだけど、
画面がパスワードでロックされている(当時はめずらしい)
ことに気付き、彼女にパスワードを打ってもらうようお願いする。
「ソラよ。ソラ」
彼女は窓のほうへ顔を向けたまま、そう答えた。
彼女の目線越しに、窓を通して真っ青な空が見える。
サマータイムが始まったばかりの、1992年のドイツの青空。
「いい天気ですね」とぼくは言い、
「パスワードを、」と彼女をうながす。
「だからソラよ。エス・オー・アール・エイ」
それは窓の外のことではなくパスワードのことだったのだ。
それだけいうと彼女は黙り、ぼくは作業に取り掛かった。
しばらくキーを叩き、問題の原因を見つけると、
もと通り動くように、いくつかコマンドを打ち込む。
そのあいだずぅっと彼女はとなりに座ったまま、
窓の外を眺めていた。
「あら、コーヒーも出さずにごめんなさい」
彼女がそういったのは、ぼくが作業を終え
帰り支度をしているときだった。
「またなにかあったら連絡ください」
そう言いながらお辞儀をし、オフィスの出口へ向かう。
パスワードは “sora” 。 それは
いまにして思えばあまりにもシンプルで、儚(はかな)い。
たぶん彼女は、画面をロックしたかったのではなく、
毎回ただ ” s o r a ” と入力したかっただけなのだと思う。
確信はない。 ただそう思っただけだ。
真偽はともかく、ぼくが彼女を見たのはそれが最後だった。
ぼくが他人のパスワードを知ったのもそれが最後だった。
でももう、そんなシンプルなパスワードは許されない。
2010年の世界にあっては。
便利への代償は少なくないものですね
![]() 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ
よろしければクリックくださいね









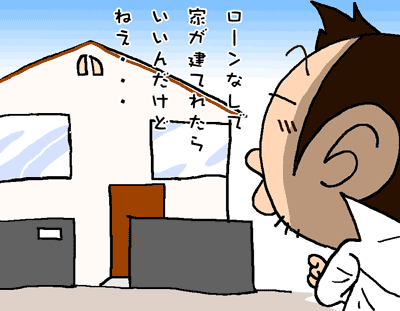

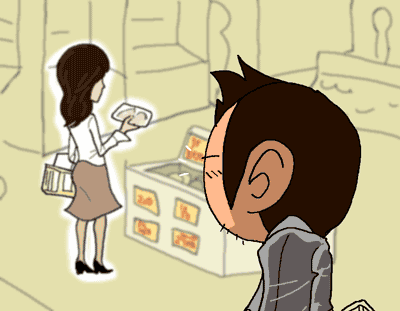


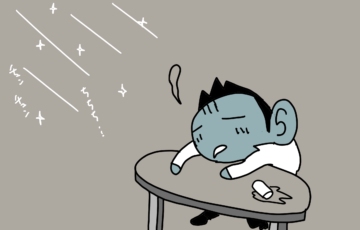
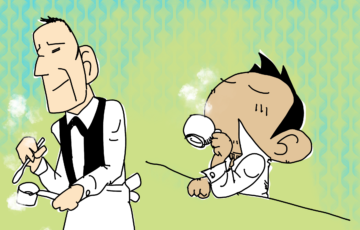
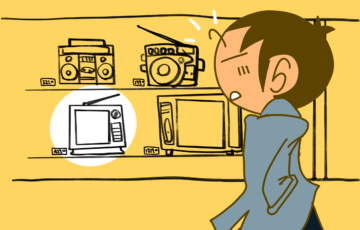
最近のコメント