パリで暮らしていたころの記憶は意外と少ない。
自分でもおどろくほど印象が薄いのだ。
ふだんはまずたどらない記憶の数々が、ここさいきん
不思議なことにあれこれと思い出されるのだ。
これはいったい、どうしたことだろう?
会社が用意してくれたアパルトマンは
凱旋門から徒歩10分という好ロケーション。
だのにぼくは、ものすごく地味な暮らしぶりであった。
小さな単身赴任者用のストゥーディオタイプで、
はしごで上り下りする小さなスペースにベッドがあった。
ロマンチックのかけらもないテーブルにワインのボトル。
赤ワインが苦手になったのはちょうどそのころである。
着任したのは1994年の、ちょうど今ごろの季節。
陽は日毎長くなり、新緑はまぶしく、あたたかだった。
欧州全体で一年でもっともすごしやすい時期なのだ。
職場はパリ西部の郊外にあった。
そこへはドイツから乗ってきたアウディで通った。
ぎゅうぎゅうに詰まった路上駐車から
車を出すのは、ことのほか面倒だったし、
朝のラッシュ時の凱旋門のロータリーと、
さらに北にあるポート・マヨールのロータリーを
ぐるぐるまわりながら通り抜けるたいへんさは
経験した人でないと、ちょっとわからないと思う。
何度もミラーをこすられ、神経をすり減らされた。
これで一日の半分のエネルギーが消耗される。
残りは夕方のラッシュと、
自宅付近で駐車スペースを探すことに消耗された。
仕事で使うエネルギーなどほとんど残らない。
ましてや帰宅後においてなど・・
職場に着いて最初にすることはコーヒーを飲むことだった。
すでに小さなパントリーに各部署から社員が集まっていて、
それぞれ小さなカップを、つまむようにして口に運んでいる。
ミルクも砂糖も入れない。 全員がブラックだ。
「キャフェ・オ・レは飲まないの?」と訊けば、
「あれは家で飲むものさ」と返ってきた。
フランス語が満足に話せなかったこともあり、
オフィスでの居心地は悪かった。
営業の担当者と、黒人女性秘書がひとりずつ同じチームにいて
彼らはなんとか通じる英語を話した。
ぼくも負けじと覚えたてのフランス語を話したが
たぶん、頭の悪いひとのように思われていたはずだ。
パリに友達はいなかった。
休みの日は朝から映画を観て時間をつぶした。
名画座のような小さな映画館を探し、そこで
コーヒーを飲み、バケットを食べながら映画を観た。
ゲイばかりの映画館に間違えてはいってしまい、
あわてて逃げ出したこともある。
パリのレストランにひとりで入るのは心理的にしんどい。
なので日本人観光客に声をかけて一緒に食事をしたりもした。
こういうのもなんだかナンパ師のようで、1度でやめた。
以後食事はもっぱらファーストフードか、家で食べた。
古い紙のように寂しく、プールのそこにいるかのような孤独感
そのような記憶が「おり」のように脳の底に沈殿する。
パリはひとりで過ごすに適さない。 トーキョーとは違うのだ。
パリで暮らしていたことを人に話すことはあまりない。
セーヌもエッフェルも、その頃の記録にない。
あるのは、苦労して探す駐車スペースと、苦いコーヒーの味。
それから時代に取り残された古い映画館の柔らかすぎるシート。
あれから16年も経ったことに、今さらのように気付く。
パリで暮らした記憶よりも、いま暮らす東京のほうが遠くなる。
記憶の中の遠近法が、たまに狂っちゃうことがぼくにはある。
記憶はゆっくり自転しているんじゃないかとぼくは思うんですけど








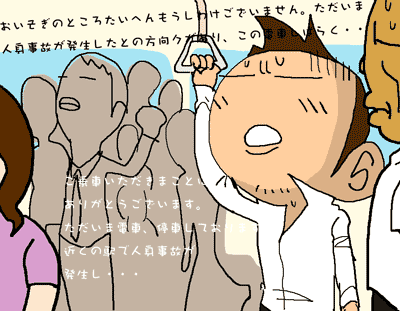

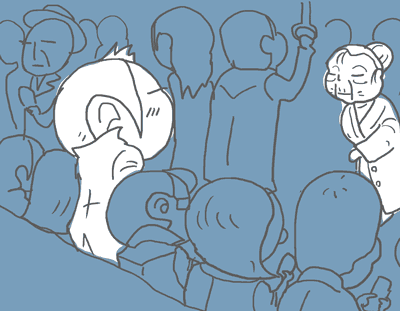
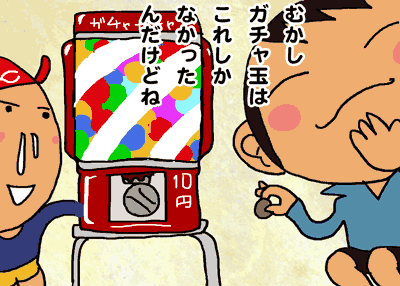

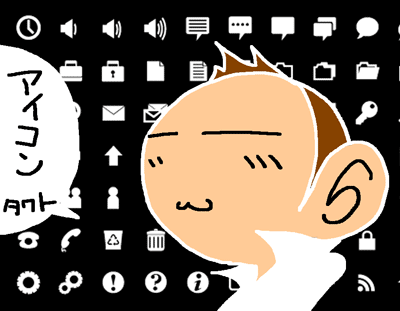

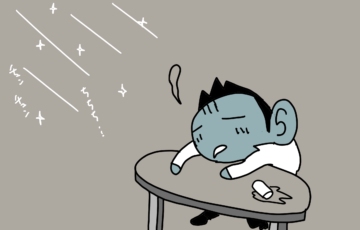
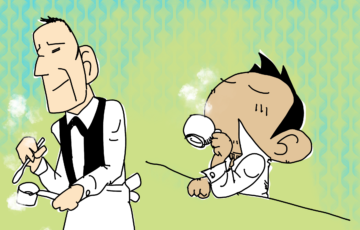
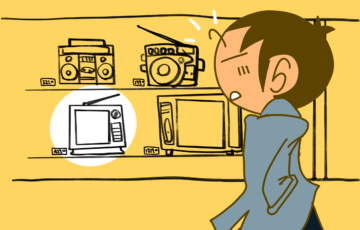
最近のコメント