あれはまだぼくが就職したばかりのころだっただから、
もうずいぶん昔のことだ。
あの頃の自分は今の100倍くらい、ネガティブであった。
慣れない社会人生活は、慣れない外国生活でもあり
慣れない人間関係は、慣れない外国語のせいでもあった。
日本語ですらよくわからない商談を、
英語でやらなくてはいけない苦痛と、
英語だってろくにしゃべれなれないのに
ドイツ語しか通じない生活環境の中で暮らしていた。
もしそれが「暮らし」といえればだが。
いちにち10マルク以内、それがぼくのきめた小遣いだ。
タバコ一箱が4マルクしていた時代である。
職場の先輩たちは、新人、とくにぼくに冷たかった。
ろくに仕事など教えてくれなかった。
仕事上がりに研修はあったが、その時間をぼくは
ドイツ語学校に通うことに費やした。
でも実際のところぼくはそんな授業をさぼり、
なじみの飲み屋街に足を伸ばした。
学ぶべき多くのことは、まるでそこにあるかのように。
実のところ研修をさぼって飲んでいた、というだけだが。
ストレスは最高潮にあり、エネルギーをもてあましていた。
自分は誰であり、何が出来るのか?
まずは日本人であり、それは生活においてデメリットだった。
アーリア人によるアジア人への偏見はあったのだ。それなりに
そしてあの頃のぼくは何ひとつ満足にできなかった。
土曜日の朝は、たまった洗濯物をバッグに詰めて
コインランドリーへ通うのがささやかな楽しみであった。
週に一度とはいえ、通勤よりも熱心に通った。
なにしろそこはぼくのお気に入りの場所のひとつ。
短い夏をのぞいては、ドイツはそれなりに寒い。
通りに面したガラス張りの室内はとてもあたたかく
洗剤の放つ、清潔なにおいに満ちていた。
そこにいるだけで身体が洗われる気がした。心もだ。
ぼくはそこで朝食をとることを常とした。
途中立ち寄るパン屋で買うものはだいたい決まっている。
クロワッサン2個とスモークハムとチーズ、
そしてたっぷりのコーヒー。 それからバナナも。
そのコインランドリーにはきまって浮浪者がひとり居た。
名前をオリバーというその男は老齢で、顔半分が髭だった。
哲学者のようでもあり、しかしただのホームレスである。
ほかに中央駅のベンチで寝ている姿も見かけていたから。
ある土曜日、クロワッサンをひとつあげたことをきっかけに
オリバーとぼくは、互いに会話するようになった。
それはとても会話とは言えない会話である。
彼はドイツ語しかしゃべれず、ぼくは片言でしか返せない。
翌週からぼくは小さなスケッチブックを持ち込んだ。
筆談である。 いや、絵談というべきか。
もとよりぼくのイラストはコミュニケーションが発祥だ。
それにしてもオリバーの絵は、笑いをとるのに十分だった。
犬がサイに見え、ビール瓶がまな板に見えた。
彼はソクラテスのような顔をして、5歳児のような絵を描く。
大まじめな顔が、むしろ愉快でならなかった。
そして彼は、ぼくを、ひとりの人間として扱ってくれた。
なにひとつできず、自信を失っていたぼくに。
やがて、初めての夏をその土地で迎えるころ、
オリバーはコインランドリーから、突然いなくなった。
その後何週間も彼を姿を見かけることはなかった。
中央駅のベンチにもいなかった。
前もってあいさつはなく、兆候も見あたらなかった。
ぼくはいつものコーヒーを飲み、クロワッサンを食べながら
しかしいつも以上に大きな音を立てて回る乾燥機を眺め、
入り口に積んであるフリーペーパーを開いては閉じ、
それに飽きると、何冊目かのスケッチブックを広げた。
思いがけず最後の会話となったぺージを開く。
どう見てもやっぱり象にしか見えないタカの絵の下に
いつの間に書かれたのであろう彼の残された一文を発見する。
“Du bist mir ein feiner Freund!”
(おまえはなんていい友達なんだ!)
新緑の木漏れ日が通りに面したガラスから差し込み、
古く巨大な乾燥機の丸い窓枠を、きららかに照らしていた。
以来ぼくは、ついにオリバーをふたたび見ることはなかった。
それはまだベルリンに壁があったころの、ちいさな出来事。
あれからまたたく間に25年の月日が過ぎていったけれど
コインランドリーにはもう、しばらくいっていない。
あのコインランドリーはまだあるのだろうが、
オリバーはもうこの世にはいないことくらい
ぼくにもわかる。
「あの頃の・・」が会話に出てくるようになったら要注意ですね
![]() ←この記事はイラ写ベスト20に選ばれました。ブログランキングへ!
←この記事はイラ写ベスト20に選ばれました。ブログランキングへ!














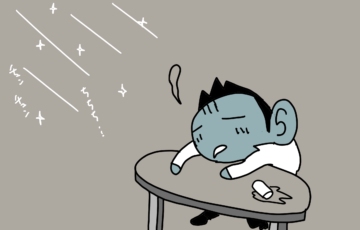
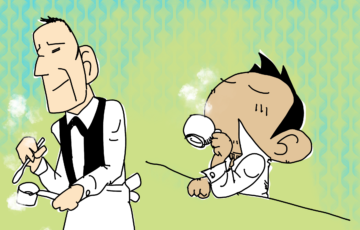
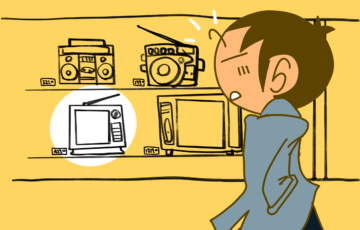
最近のコメント