母親が家を出て行ったのはぼくがまだ6歳のとき。
小学校の入学式までは母親が一緒に写っていたが、
それ以後の写真にその姿はなかった。
ぼくは母親の残していったエプロンを締め、
ひとりで食事を作り、ひとりで食べた。
ひとりで風呂を沸かし、ひとりではいった。
ぼくが6つか7つのとき、父親は仕事が忙しく
帰宅するのはたいてい、ぼくの眠ったあとで、
出勤するのは、ぼくの起床する前だった。
そのような環境が
「自分は特別」というなにか自負のようなものを
幼い心に醸成させていったのかもしれない。
「母親に甘えるなんて幼稚な子供のすることだ」
なんてことを、わりとふつうに思っていた。
小学校低学年のガキが、である。
「愛情は無償ではなく、また無限でもない」
中学の卒業文集にぼくは、そんな一言を残した。
世間というのは、たとえば弱者に同情的である。
「同情」という心理そのものは実に尊い。
けれども同情を受けるものからすれば複雑だ。
一方的なほどこしは、ときに負債感を与えもする。
「この人は自分より私を下に見ている」
受ける側にそんな思いを抱かせるに十分だ。
マズローのいう「親和の欲求」と「尊厳の欲求」
それが十分満たされないまま「自分らしく」をめざせば
ぼくは人と違うことをひたすら突き進むしかなかった。
ぼくは一刻も早く自分を試したかった。
よほどのどが渇いていたのだろう。
大学を卒業するのももどかしく、
海外赴任をめざして野心高く就職し、
ドイツに住み始めると、まもなく結婚。
相手はドイツ人、22のときである。
ぼくは一度に多くのものを欲したのかもしれないし
あるいは、何も欲しなかったのかもしれない。
「外国人として暮らす」というのは幸いだった。
生まれた国を端から眺め、世間に惑わされず、
じっくり身の回りのことを考えることができた。
自分の形を成す輪郭というのは、
いちど外してみないとわからない。
自分が周囲とどれだけ違うかを知る。
自分がいかにちっぽけな存在かを知る。
自我を一度脱ぎ、ふたたび着直す。
そんな作業が、外の暮らしにはあった。
結局のところ、欲しがっているだけではダメなのだ。
「愛されたい」ではなく、愛してあげる。
「承認されたい」ではなく、承認してあげる。
欲しいものがあれば、まず自分が与えることを考える。
やってほしいことがあれば、まず自分がやってみる。
人生で何をしたかは、仕事や所有したものではなく
どれだけ人に与えたか、で決まるのだとつくづく思う。
親や、会社や、国が、自分になにをしてくれるのか?
ではなく
親や、会社や、国に、自分が与えられるものは何か?
こう考える。
幸せになりたければ、まず与えること。
ぼくはそのことを、しばし考えている。
遠回りしながらも。
その人が何であるかは「与えるもの」の大きさで決まるのだと思います、けっして「所有しているもの」なのではなく
![]() ←最後までお付き合いくださいましてありがとうございます!よければポチッと
←最後までお付き合いくださいましてありがとうございます!よければポチッと








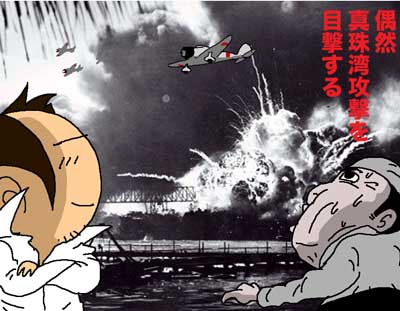





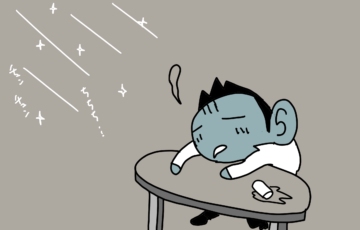
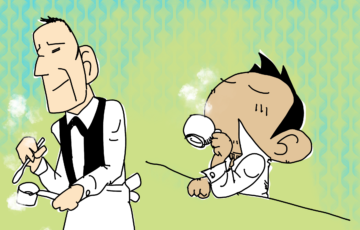
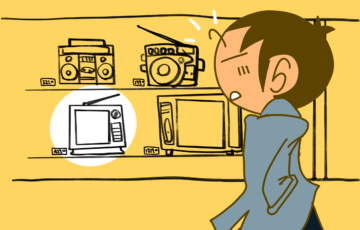
最近のコメント