
△ マッサージ屋さんで、思わぬ体験が待っていた!?
「ねえ、どこかおすすめのマッサージ屋ってある?」
屋台でSOTO(ソト)というインドネシア風雑炊に牛肉の内蔵が入ったものをすすりながら、ブディさんに訊く。 チリソースを入れ過ぎてしまい、舌が燃えるようにひりひりする。
「いいところがあるですよ、少し遠いですが」
ブディさんは大粒の汗を額に浮かべている。 やはりチリソースを入れ過ぎたのだろう。 アイスみかんジュースをひとくち飲み、ブディさんは「いぜん、キリタニさんとタカハシさん連れて行きましたよ。すごく利きます」と話す。 ブディさんは必ず第三者であっても固有名詞で語る。 彼にとって「ひと」という名前の人はいないのだ。
「じゃあ、タマン・サリ(夏の離宮)見たら、そこにいこう」
「ガスン市場はどうしますか?」
「そのあとでもいいし、いかなくてもいい」

△ タマン・サリ(夏の離宮)と、そこで記念撮影するスーク姿の女の子たち
見渡す限り水田が広がる農道を、切り裂くようにバイクは疾走する。 けれども昨日ほど軽快なエンジン音ではない。 時おりシリンダーにカリカリカリという音が混じり、ため息のような排気ガスがボワンと出る。
そんな平坦な道を20分ほど走っただろうか、いつしかバイクは村の中へ。 塔の上にスピーカーをくくりつけたモスクがあり、尖った瓦葺きの屋根や藁を葺いた農家があった。 道ばたをうろつく鶏をよけながらブディさんは幾分スピードを落とす。 歓声を上げながら庭を走り回る子供や、傘帽子をかぶった農民たちが収穫した麦を足で踏むのが見える。 おそらく50年前と変わらない光景に、ふと科学技術はほんとうに人類を幸せにしたんだろうか、と思う。
「つきました。ここです」
「ここ?」
そこはマッサージ屋さんというよりは、ぼくにはただの村の集会所に見えた。
広い縁側には竹のソファがいくつも並べられ、壁のあちこちに十字架とマリア像がかけられてある。 庭にはヤシとマンゴーの木。 受付嬢はいない。 それどころかぼくたちのほかには誰もいない。
ブディさんは靴を脱いで縁側に上がり「どうぞ」とぼくにソファを勧める。
「どうぞ」、って・・ ブディさん、あなたイスラム教徒じゃん!
ソファにどかりと座るブディさんの頭上には、マリアさまが慈悲深く微笑みになっているのだった。
「おばあさんはほかのお客さんをマッサージ中ですね、バナナ、たべますか?」 ブディさんはバッグからバナナを取り出しテーブルの上に並べる。 バナナは甘く、とてもおいしかったが、そんなバナナ・・・
「ねえ、モスクでのお祈りさぼって、キリスト教信者のマッサージ屋でバナナ食べてていいの?」 と心配そうに訊いてみる。 ジャカルタのホテルで爆弾をしかけたのは狂信的なイスラム信者なのだ。 「ゲンリシュギはダメですよ。 アルカイーダはジェマ・イスラミアを利用しているだけです」 とブディさんは言い、「それよりこのバナナ、おいしいでしょ? コウモリもこのバナナが大好きです」と誇らしげだ。 コウモリ・・・。 アッラーの神は迷える人々をいったいどうお導き遊ばれているのだろう?
穏やかな日差しの中、庭先からハーブの香りが混じった心地よい風がふいてきて、マンゴーの葉を揺らし、汗ばんだシャツを乾かす。 かごの中の鶏がココココと鳴く。
そのおばあさんが出てきたのは、それから15分ほど経ってからだった。
十字架の真下のドアが開き、中から背筋をまっすぐにのばした婦人があらわれた。 慈しみ深いその微笑みに、ぼくは思わず手を合わしたくなってくる。 うたた寝をしていたブディさんも起き上がった。
「さあ、こちらへ」と婦人はぼくを導く。
もちろん英語は話さない。 でもわかる。 薄暗い小さな部屋に通されると、そこにはせんべい布団とひしゃげた枕がひとつあるだけだ。 壁にはやはり十字架とマリア様、その横におそらく婦人の若いころの額入りの写真。 なかなかの美人だ。 旦那様と写った写真もある。 建国の父、スカルノ永久大統領の額もあった。
パンツを残して服を脱ぎ、シーツのようなインドネシア織物を身体に巻く。 なんだかおごそかな気分だ。 マッサージを受けるだけなのに。
婦人は微笑みながら「うつぶせに」という。 ぼくはうつぶせになる。 「力を抜いて、ラクにして」という。 ぼくは力を抜き、目を閉じる。 インドネシア語はわからないが、婦人の言葉はわかるのだ。
マッサージは足首から始まった。 こりこりこりこり、と指先でリンパ腺を突く。 指の一本一本がそれぞれ意志を持っているかのようだ。 今までいろんなマッサージを受けたけれど、これほど痛いのも初めてだ。 背中を何人もの小人たちに踏みしだかれている感じがする。 こりこりこりこり、とっ、とっ、とん。ととん、とん。 婦人はあまりさすらない。 その小人の足のような指先で踏むように、押すのだ。 農民の麦踏みのように、ぶどうを踏むワイン作りの女の子たちのように。(いてててて!)
マッサージは約1時間ほどで終わった。 肌に汗がにじみ、少しだけ息が荒い。 婦人も同じように肩で息をしている。 昼下がりの薄暗い個室に男女二人だけ、こういうのもなんだかちょっとエロい。 最後に全身にハーブ入りのオイルを塗ってくれる。 さっき縁側でしていた匂いと同じだ。 上半身を起こすと、相変わらず慈悲深い微笑みを浮かべた婦人の姿が見えた。うしろのドアの隙間から光が射して、その姿に後光を作り、十字架を照らした。
ぼくは思わず胸に手を合わせ、テレマカシと言った。
帰り道、バイクの音量に負けないような声でブディさんは「すごい効いたでしょ?」と何度も訊く。 ぼくは「うん、すごい効いた」とやはり何度も答え、「ありがたい気分にもなれた」と付け足した。 あたりはすでに陽が傾き、夕暮れのジャワ島の山あいからオレンジ色の雲がひろがっていた。 マッサージでもみしだかれた身体がけだるく、少し肌寒いくらいの風がシャツをいきおいよくはためかせている。 ふと、ハンドルを握るブディさんが、幼い頃からの友人のような気がしてきた。 輪廻? あるいはそうなのかもしれない。 ともかく、この光景はこの先何度も憶いだすんだろうなあと思う。
そのときだった。
突然バイクのエンジンが止まったのは。
何の前触れもなく、突然に。
とたんにあたりに静寂が訪れる。 カエルの鳴き声や牛の声、過ぎ去るバイクやクルマの騒音があらためて耳に入ってくる。 バイクはエンジンが切れたまま無音で滑走し、しばらく進んでからやがて止まった。 ブディさんが何やら言っている。 おそらく毒づいたり祈ったりしているのだろう。 バイクを横に倒し、燃料タンクの様子を見たり、キックベダルをけったりしている。 ひとしきりやってみて、やがてあきらめてぼくのほうを向く。 やれやれといった感じに。
「バイク、こわれちゃったね」 とぼくは言う。
「もうしわけないです、もうセルもまわりません」 とブディさん。
「調子、悪そうだったものね、バイク」
「ええ、たくさん走ったから故障しました」
「しょうがないよね」
「はい、しょうがないです、歩きます」
ぼくたちは二人でバイクを押しながら、田舎道をジョグジャの街のほうへ向かって歩き始める。 トラックが轟音をたててすぐそばを通り過ぎる。 通りの反対側から親子を乗せた馬車がやってきて、やがて後方へと過ぎ去る。 振り返ると、道にうんこをぼとぼと落としていた。
「街まで遠いのかな?」
「たぶん5kmくらい歩いたらタクシー乗り場があるはずです」
「バイクはどうするの?」
「修理に出します」
「そのほうがよさそうだね」
ブディさんとのバイクの旅はこのようにして終わった。
最後はジャワ島の田舎道をバイクを押して歩くというオプションを加えて。
それからたっぷり1時間ほど歩いて、ぼくはタクシーを見つけた。
「タクシーでバイクを運べないの?」 とぼくはいちおう訊く。
「だいじょうぶ、近くにバイクの修理屋さんがあるはずですから」
そういってブディさんは夕日を浴びながら悲しそうに笑う。
「テレマカシー、ほんとうに楽しかった!また逢おう」
ぼくたちは握手をして別れた。

ほんとうに楽しかったのだ。
最後のオプションで、せっかくのマッサージはチャラになってしまったのだけど。
いよいよ旅も終盤、夕方の便でジョグジャを離れ、再びジャカルタへもどります
応援ポチが身にしみます、いつもありがとうございます![]()










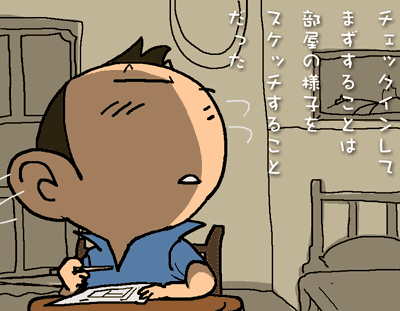


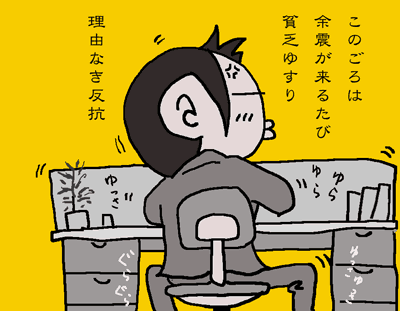

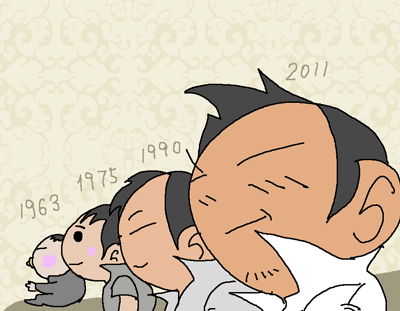

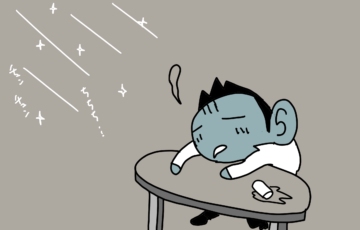
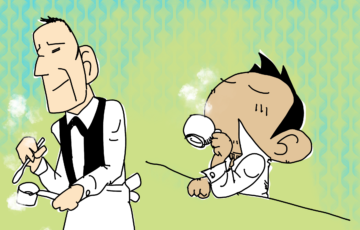
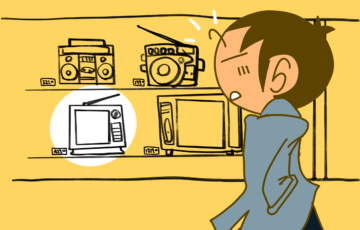
最近のコメント