
いまから82年前、ある男がこの世に生まれた。
古い家柄の長男として生まれた宿命として、個人よりも家に重きをおいて育てられた。 以来、時計のように正確な毎日をこつこつと生きることを余儀なくされ、医療技師としての教育を受けた後は、実に79歳に至るまで50年以上休むことなく歯科技師として入れ歯や詰め物などの製作し続けた。 やがて技術の衰えを感じ、3年前に引退した。 その後は趣味の日本刀や古銭のコレクションに没頭し、静かに余生を過ごしていたのだけど、先日腎不全を患い肺炎を併発して静かに息を引き取った。
その男とは、ぼくの叔父のことだ。
子供の頃からぼくは叔父が苦手だった。 自分に厳しく他人に厳しい、昔ながらの人だったからだ。 古い家を継ぐ長男としての責務を全うするには、親族すべてに対し厳しくするしかなかったのであろう。 けれども事情をよく知らない幼少のぼくにとっては、無駄にうるさい存在でしかなかったのだ。
ぼくが高校を卒業するとさっさと広島を出たり、社会人になる際に海外を目指したのは、この叔父への反動があったのかもしれない。 そういった意味で、叔父はぼくの人生に少なからず影響しているといえる。
葬儀に参列したぼくは、仏前におかれた叔父の棺桶を見て、「おや?」と思った。
棺の上には、遺影や白い折り鶴に混じって「旧海軍の軍帽」が乗せられていたからだ。 参列者の中には旧海軍の制服を着る老人もちらほら見られた。
1943年、同盟国のイタリアが降伏した直後、叔父は学徒出陣により海軍に入ったのだという。 初耳だった。 ぼくがそのことを知ったのは葬儀のこの日のことだったのだ。 出陣した叔父は海軍に編入後三大軍港のひとつ呉に勤務し、広島湾の巡洋艦で厳しい訓練を受けていた。 訓練後は、あの戦艦大和に乗艦することが決まっていたのだと叔母はいう。
映画 「男たちのYAMATO」 を観に、叔父はひとりで何度も映画館に足を運び、そのたびに真っ赤に腫らした目をして帰ってきたのだという。 映画のストーリーにあるとおり、沖縄特攻へむかう途中大和は鹿児島の西方で米軍機の爆撃にあい、奮戦の上沈められてしまう。 このとき叔父は横須賀へ出張に行っていたために、大和と運命を共にしなかったのだけど、共に猛訓練を受けた多くの若い戦友たちをこの瞬間、失った。
「わしも一緒に死ぬはずだったんじゃ・・」
生前、酔うと叔父はそう叔母に漏らすことがあったのだけど、それは生き残ってホッとしたというよりは、生き残ったことで同期の戦友達に顔向けできないといった罪悪感に満ちていたそうだ。
戦後生き残った多くのおじいちゃん達は、叔父同様そんなふうに戦争を多く語らないまま、生涯を閉じていった。 もしかすると叔父は 「男たちのYAMATO」で、主役の神尾(仲代達也)に自分を重ねてみたのかもしれない。 映画のシーン同様、生き残った神尾は死んでいった戦友たちの生家を訪ねて回ったが、叔父もまた同様だったようだ。 戦後になって大和が沈んでいたことを知った(戦中は秘匿とされていたそうだ)叔父は、帰還後死んでいった戦友の生家を訪ね、手を合わせて回ったのだという。
しかし労苦の果てにようやく帰還した叔父を待っていたのは、原爆によって壊滅させられた広島の街であった。
叔父の世代とは、そんな悲しい時代だった。
高温のかまどで焼かれた叔父が今は白骨となって目の前に広がる。
戦後は一貫して、こりこりと義歯を作りながら生きてきた叔父。 どこにも旅行に行かず、生涯のほとんどを自宅の作業室の中で過ごした。 それはまるで時計が針を刻むように正確な毎日だったという。
同じ姓を名乗り、お互いにどこか顔の作りが似ているぼくたち遺族は、やがて火葬された叔父の骨を大きな箸でつまみ、骨壺へと落とす。 その骨は水分もほとんどなく、焼かれたというよりは、たったいま出土されたといった感じだった。
小さな骨壺は、いくつかの骨を入れるとすぐにいっぱいになり、入りきらない骨はそのまま台の上に残された。 他の参列者が次々と部屋を出て行くあいだも、しかしぼくはどうしてもその残った白骨から目をそらすことが出来ない。
最後は係員にやんわりと促され、しぶしぶ出て行く始末だった。
それは生きとせ生きる者たちに平等に訪れる、なりの果てだった。
それにしても叔父は生前、心から幸せだったのだろうか? それとも戦友の多くや大和と一緒に運命を共にしたかったのだろうか?
もちろん今となっては知るよしもないけれど、やむを得ないとはいえ死んで愛する人を守るより、生きて守る方が何倍も大変なことだと思う。
本家からの帰り際、叔母から 「叔父の形見」 にとロレックスをいただいた。 耳に当てるとこちこちと針を刻む音がする。 叔父の生前のように規則正しく、そして正確に。
「持ち主がおらんなっても、時計は止まらんのじゃねぇ」
ぼくがそういうと、叔母は堰を切ったように泣き崩れた。 喪主として葬儀も無事に完了させ、いまようやく緊張が解けたのだと思う。
一途に夫を支えてきた女の涙、
あるいは砲弾よりも強いんじゃないかと、そのときふと思った。

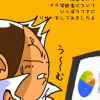


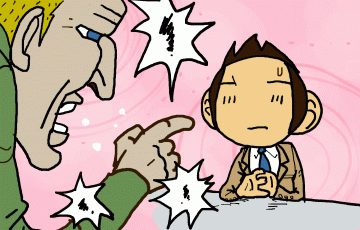



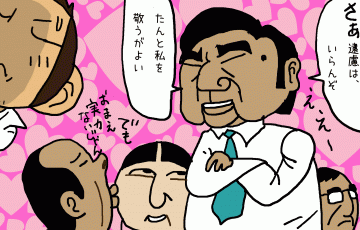

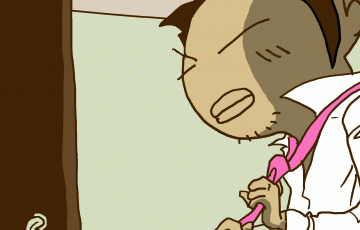

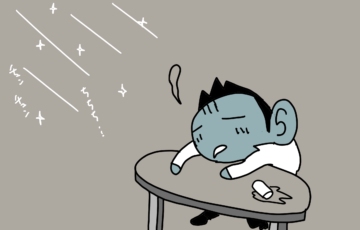
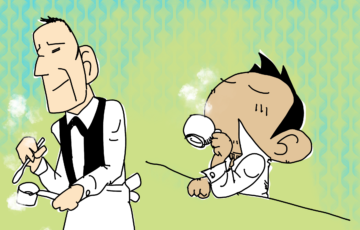
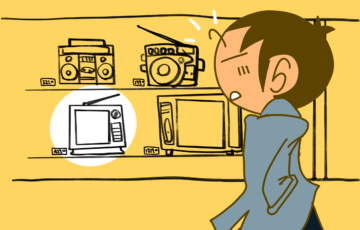
最近のコメント