
今回のイラ写は、ちょっとコワイかもしれません。
「霊現象」といえなくもないけど、いわゆるユーレイ話でもないし、スプラッターホラー系というわけでもない。 もしかするとちっともコワくないかもしれない。
「怖い話はちょっと苦手で・・・」
てな方は、下の脱出リンクを押して「他の絵日記ブログ」へ退避してください。 あとで「夜眠れなくなったじゃない!」と抗議されても責任は取れませんので。
でも、「カレーライス」と「コワい話」はどこか似てますね。 「カラいけど美味い」と「コワいけど面白い」
ではまいります。
心の準備はよろしいでしょうか?
1988年の晩秋から1990年の初春まで、ぼくは妻と猫と一緒に、京王井の頭線の久我山駅そばのマンションに暮らしていた。 駅から歩いて1分という物件で、ベランダからは駅のホームが見下ろせた。 便利だけど、電車が運行している時間帯はうるさ過ぎて、とても寝ていられなかったのを覚えている。
バブル真っ盛りということもあって、当時勤めていた会社からは年に5回もボーナスをもらうなど、羽振りはよかったと思う。 周りのダレもが羽振りよかった時代だから、特にぼくだけが目立っていたワケじゃないけど・・・。
当時の仕事はもう宿命的に忙しかった。 午前中は貿易の仕事をし、午後からは現場(店舗)で作業していた。 会社はアパレル関係だったが、多角経営の一環で4つのレストランとカフェバーを経営していて、ぼくがその管理を任されていたのだ。 一日の最後の仕事はカフェバーの鍵を閉めて、売上金を銀行の夜間金庫に投函すること。 それが終わって家に着くとだいたい2時半をまわっていた。 朝方まで飲み歩くこともあった。 ぼくはまだ20代で、今よりも遙かにエネルギッシュでダイナミックな毎日を過ごしていた。
そのころのぼくは、よく金縛りに遭っていた。 正確に言えば「そこのマンションに住んでいる間」、しょっちゅう金縛りにあった。 「金縛りのパターン」はだいたい一致している。 まず夜更けに唐突に目が覚める。 それから胸のあたりに上から押さえつけられるような重力を感じる。 ぱきぱきっという音が聞こえる。 耳鳴りがする。 そして身体がまったく動かなくなる。 いや、目を覚ました瞬間から、とっくに動かなくなっている。 動くのは唯一眼球と舌だけ。 それ以外はまったく動かない。 声もでない。
気配を感じる。 「何か」が動くというよりは「空気全体」が渦を巻くように動いている気配。 奇妙な質感のある空気。 それが頬にざわざわっと触れることもある。心臓がばくばくする。 口の中がカラカラになる。 声を上げて隣で寝ている妻に知らせたい。 なのに、「ぐぐ・・」とか「うう・・」とくぐもった声しか出せない。 まぶたを固く閉じる。 目を開ければそこに「何か」を見るかもしれない。 その「何か」と目が合ってしまえばおしまいだ。 そんな確信があった。 だから目を開けることが出来ないのだ。 心の中で「帰れ!」と叫び続ける。
「ここはおまえの来るところじゃない」、と。
しばらくすると、突然カラダが軽くなる。 耳鳴りが消える。 「それ」は唐突に始まり唐突に終わる。 はじかれたようにぼくは上体を起こす。 サイドテーブルに置いてある飲みかけのウイスキーをごくりと飲む。
というのが、だいたいのパターンだ。
けれどもその夜は違った。
例によって金縛りに遭っている間、
「何か」がぼくの左手を「はしっ」とつかんだからだ。
その夜はぼくひとりで寝ていた。 妻はドイツに一時帰省していたし、普段はぼくの腕枕で眠っている猫もどこかへいってしまっていた。 「その手」は妙に湿っていて、ひんやりとはしていなかったが、ぬくもりもなかった。 湿っていてぐにゃりと柔らかい手 ・・・ おそらく手だろう、と思う。 確かめようにもぼくは目を閉じていた。 怖くて開けられない。 身体は動かない。 もちろん声もでない。 ぼくは「それ」が去るのをじっと待っていた。 他に何をすればいい?
そのとき、ぼくのすぐそばで、「それ」はしゃべるのだった
「いい・・・指輪・・してるわねえ・・・」
太くかすれた声。 女? 知るもんか! とにかく身体は動かないのに、その声が聞こえたせいで、身体が3センチほど飛び上がったように感じた。 信じられないくらい不気味な声。 後にも先にも「声」を耳にしたのはこのときだけだ。
ここまで恐怖に陥れる「それ」に、ぼくは腹さえたってきた。 左手にはまだぐにゃりとした感触がある。
ぼくは思い切って目をあけてみた。 くわっ!
すると・・・・!
・
・
・
・
・
・
・
期待した「それ」は、そこにはいなかった。
代わりに見えたのは・・・
ベッド
「だだっ広いベッド」が、そこにあった。
いつの間にかぼくの寝ているベッドがずっと先まで伸びている。
いつもダブルベッドの左側で寝ているぼくの横は当然、「ベッドのはし」であり、電気スタンドや本、ウイスキーのグラスが置かれたサイドテーブルがあるはず。
だのに、視界にあるのはベッドだけ。 6mはあるだろうか? べろ〜んと引き延ばされたように広いベッド。 その上でぼくが寝ているのだ。
首が回らないので、目玉をそーっと動かしてそのベッドの先に視線を向ける。 6メートルくらい先にぼんやり明かりの灯る電気スタンドが見えた。 その電気スタンドに映し出されているのは、女の子。
女の子はノースリーブのネグリジェを着ていた。 顔は長い髪で覆われ、ベッドにうつぶせになって本を読んでいる・・・。 なぜかぼくと同じベッドで、しかもこんなに大きなベッドで。
その女の子は、ぼくには気づいていないようだった。 髪に隠れて顔はよくみえない。 鼻先がほんの少し見えるくらいだ。 そして、ベッドの上に広げた本をむさぼるように読んでいる。 ステンドグラスでデザインされたシェードが乗っかった電気スタンドが、まるでスポットライトのように彼女を淡く照らしている。
いつの間にか左手にあった例の感触はなくなっていた。
どのくらいの時間が経ったのか、ぼくは確かめようもない。 身体はまだ動かないし、ベッドは広いままだ。
「おそらく夢だろう」 と思ってみる。 夢のわりには意識はしっかりしていたが、目の前の現象はあまりにも非現実的すぎる。 ぼくの手をつかむ「何かの感触」、不気味な声、突如現れる巨大ベッド、そして、うつぶせで本を読む女の子・・・
ありえない!
ふと、彼女の様子に異変が起きる。 本を閉じ、上体を少し起こそうとマットについたヒジを動かそうとしている。 ぼくは、彼女の身に何が起こったのかを知っている。
そう、彼女はぼくに見られていることに気がついたのだ
彼女の首がこちらに向けてゆっくりと動く・・
一定の速度でぐりぐりぐりっと首がこちらへ回転する、それが少し離れたぼくの真横で起こっている・・・
目が合ったらこんどこそおしまいだ!
身体中に戦慄が走る。 しかし、もう目を閉じることが出来ない。
彼女の顔が完全にこちらを向く瞬間、
ぼくは大声を上げていた。
中沢・・・さん!?
そこで目が覚めた。
広いベッドも、ステンドグラスの電気スタンドも、中沢さんも消えていた。
目を覚ましたぼくはとっさに時計を見た。 デジタル時計は「AM 3:27」と表示されていた。 ベッドを抜けキッチンへ向かい、冷蔵庫からミネラルウオーターを出してごくごく飲んだ。 身体は冷たい汗でびっしょりだった。
中沢さんとは、ぼくが受け持っているお店でバイトしている女の子だった。 物静かでおとなしい子。 どちらかといえば客商売に向かない女の子だ。 普段は髪をアップにしているので、下ろした髪は初めて見たが、まちがいなく「それ」は中沢さんだった。
翌日ぼくはお店で、彼女が出勤してくるのを待っていた。 心のどこかで「もしかすると彼女はすでに・・・!?」という懸念もあった。
けれども中沢さんはちゃんと出勤してきた。時間通りに。
ユニフォームに着替えて出てきた彼女にぼくはさっそく聞いてみる。 でもまさか「昨日の夜中、本を読んでなかった?」とは聞けない。 きっと彼女に怪しまれるに違いなかったから。
「目が腫れているようだけど昨夜は遅かったの?」
とぼくは彼女に言った。 彼女ははじめ不思議そうな顔をしていたが、「ええ、眠れなくて本を読んでいました」と答えた。
眠れなくて本を読んでいました
と中沢さんは言った。
それから一週間後、ぼくは結婚指輪をなくした。
ドイツへ移住してから新しいのを買ったが、それもなくしてしまった。
「いい・・・指輪・・してるわねえ・・・」
あの恐ろしい声は、いまでも耳に残っている。
その後、中沢さんの消息は、もちろん知らない。
久我山のマンションで金縛りに遭いながら、「ここはおまえの来るところじゃない!」 とぼくは心の中で叫び続けた。
けれども今にして思えば、「あの場所」にいてはいけなかったのは、「ぼく」のほうだったのかもしれない。












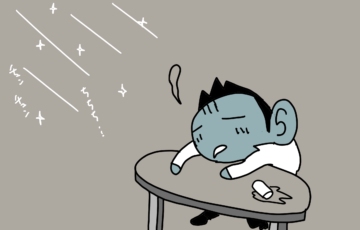
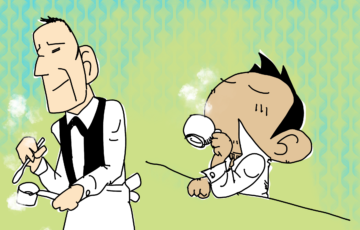
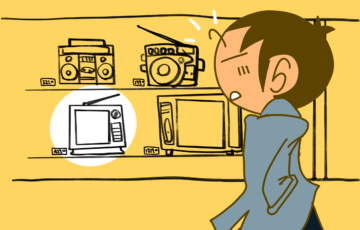
最近のコメント