
1995年の春、初めて触れたインターネットにぼくは「これで世界は変わる」と直感した。
いや、変わってしまったのはぼく自身だったのかもしれない。 当時ぼくは米国の某大手コンピュータ会社のドイツ支店が運営する日系企業向けの代理店へ出向していて、独自の有料コンピュータネットワークをシステムごと販売していた。 にもかかわらず、ぼくは会社の利益に直接結びつかないインターネットの有用性ばかりを客先やセミナーで説いてしまい、それが経営者の逆鱗に触れてしまったのだ。 今でこそ、その会社はインターネットソリューション商品を利益の源泉としているが、10年前ではいささか早すぎたのだろう。 ぼくはあっさり辞表を提出し、胸につけていたバッジをはずした。 まわりの同僚や友人は「もったいないことするなあ」とぼくを諭すが、当時の妻は「あなたはあなたの思うことをすればいい」と、あっさり認めてくれた。
こうしてぼくは失業者になった。
思うことがあって、一ヶ月後には地元ドイツで個人事業を立ち上げ、さっさとロンドンへ移住してしまう。 ある会社と業務委託契約を結びそれを履行するためと、立ち上げたばかりのインターネット関連会社を友人と共同経営するためだった。
なけなしの資金をムダにしたくなかったぼくは、愛車にパソコンと詰め込めるだけの身の回り品だけで単身、ドーバー海峡を渡った。 ハマースミス駅のそばに小さなアパートを会社で借りて住み、そこから歩いてオフィスに通った。
思えば、ロンドンでの生活は今の東京の生活とちょっと似ているかもしれない。 そこで待っていたのは、休日もなく連日20時間近く働く毎日だった。 たまに自由な時間が取れると、チャーリングクロスの本屋に足を運び、帰りにピカデリーサーカスのHMVへ立ち寄った。 レスタースクエアの映画館で時間を潰し、チャイナタウンの安レストランで食事をした。 仕事仲間以外に友人はほとんどいなかったが、ごくたまにパブでビールにつきあってくれる女の子がいた。
ロンドンでの生活はあわただしく、不思議なほどに記憶がない。 それより今でも懐かしく想い出すのは失業時代の一ヶ月の出来事。 会社を辞め、ロンドンに渡るまでのあいだ、ぼくは毎日遊んで暮らしていた。 それはいくつもの長いトンネルをくぐったあとの、開放感に包まれた至福の30日間だった。 背負っていた荷物をすべておろしたときの、あの感覚。 おろしてみて初めて気づく「荷物の重さ」に少なからず驚いた。 次にあらわれる別のトンネルのことは極力考えず、人生のインターバルを楽しんだ。
まさに「主夫」の毎日だった。 会社勤めの妻の代わりに家事のすべてを受け持った。 毎朝掃除や洗濯をおこない、それが終わると食料の買い出しにでかけた。 昼はスパゲティかサンドイッチを作って食べ、夜は二人分の料理を作った。 午前中にだいたいの家事は片付いてしまったから、天気のいい日は午後からライン川のほとりへと出かけた。 何冊かの本とポットに入ったコーヒー、ごくたまに大好きなフランケンワインを持ち込むこともあった。
ベンチに座って本を読み、目が疲れると目の前の川を眺めながらポットのコーヒーを飲んだ。 雨の日や肌寒い日は近くのカフェのドアをくぐり、カプチーノを飲むこともあった。
ある日、リュウイチという日本人ピアニストがやってきて、やがて毎日彼と会うのが日課となった。 坂本龍一と同じ名をもつ彼は、午前中は地元の音楽大学でクラスを受け持つが、午後は授業もないのでこのあたりでぷらぷらと散歩をしているのだ。 こんな時間にヒマをもてあそんでいる日本人なんていなかったから、彼はとてもうれしそうだった。 ポーランドやイタリアへ演奏旅行へでかけることも多いのだけど、ぼくの失業期間はちょうど彼もヒマで、こうしてベンチに二人で座って、行き交う人や船を見つめながら、とりとめのない話しをした。
どこか吟遊詩人のようでもありスナフキンのような彼とは歳も同じだったということもあって、なにかとウマがあった。 昼間からビールを飲みながらビリヤードに興じたり、予約した私営コートでテニスをした。 彼はとてもしなやかな動作でテンポよくボールを打つ。 まもなく二人で地元の試合に出場したりした。 また、週末はオランダの国境の町へ買い物がてらドライブに出かけることもあった。 そこは、ドイツよりも嗜好品や乳製品が1〜2割、安かったからだ。
「ロンドンに行くことに決めたよ」
ある日、いつものようにベンチで川を眺めながら彼にそう告げた。
「そうかあ、寂しくなるなあ」
リュウイチは顔も向けずにそう返事した。
ロンドンへ出発する2日前、ぼくは彼の家に遊びに行った。 門出を祝いたいと、仕事以外ではほとんど人前では弾かない生ピアノを、ぼくのために弾いてくれるという。 彼の家はデュッセルドルフの低所得者向けのアパートが並ぶビルク地区にあり、中庭に面した納屋を改造した平屋一戸建てにガールフレンド(今は奥さん)と暮らしていた。 大家であるセルビア人の老夫婦は大のピアノ好きで、練習する彼の演奏が聴けるのならと、ほとんどタダ同然でそこを貸しているのだという。
小さな庭に、革製の古いカウチがでんとおかれ、傾いた小さな丸テーブルがそばにあった。
「ここに座って星でもみててよ」
と彼はそう言い残し、家の中に入ると中から部屋の灯りをつけた。 正面の窓越しに、ぼうっとグランドピアノがあらわれた。
こうして、演奏者ひとり観客ひとりのミニコンサートが開演した。 モーツアルト、ショパン、リスト・・・、知っている曲もあるし全く知らない曲もある。 イタリアで開催される世界的なコンクールでの優勝実績もあり、ポーランドではCDも発売しているという彼の演奏はもちろん素晴らしいのだけど、満天の星空の下、持参したワインを自ら飲みながら生ピアノを聴いているというシーンに酔った。 もしぼくが女だったら「まちがいなく恋に落ちる」というシチュエーションだ。
20分くらい演奏したあと、家の中から出てきたリュウイチはタバコに火をつけながら、「何か弾いて欲しい曲はある?」と聞くのだった。 ぼくは、坂本龍一の「戦場のメリークリスマス」を彼にリクエストした。
オリジナルよりややスローなピアノの旋律は、まさに「カラダにしみいる」といった感じで、ぼくは目を閉じたまま顔を上に向け、一音も逃すまいとじっと演奏に聴き入った。 呼吸するのもためらわれるくらいの物悲しいメロディが、あたりの草木にも染みていく。 途中で目を開くと群青色の空一面に、ぱあっと星がまたたいて見えた。
またたく星に「明日は雨かな?」と思ったが、そうではなかった。
大粒の涙が、レンズのように左右の瞼にのっていたからだった。
それから、ダムが決壊したかのように次から次へと涙が流れた。 飲んだワインがぜんぶ涙になったかのようだった。 映画では泣けなかった「戦場のメリークリスマス」を、ぼくは彼の弾くピアノに泣いた。
それはほんとうに、涙で心が洗浄されるような演奏だったのだ。
まさに、「洗浄のメリークリスマス」・・・
シャレかよっ
■ ”リュウイチ”こと Ryuichi Morita (当然左側の男性ね)
その後、リュウイチはどうしてるかなあ? (もともとぼくらは筆無精だし、彼は今どきメールアドレスもないので)と、ネットで検索したらばっちりヒットしました。
いまは、ペトラ・ケスラーというフルート奏者と一緒に”Duo Diverso”というデュオを組み、ドイツを中心にポーランドや韓国でも活躍中の様子です。 もともとどちらかというと中国人に似た風体だったので、こうしてチャイナ服を着ると、もう「まんまじゃん!」てなことになってます。 彼と最後にあったのが2000年の春。 写真を見る限り、ぜーんぜん、変わってません。 懐かしいなあ。 ぼくもがんばんなくっちゃ! なお、リンク先はコンサートのプレスリリース(ドイツ語)です。


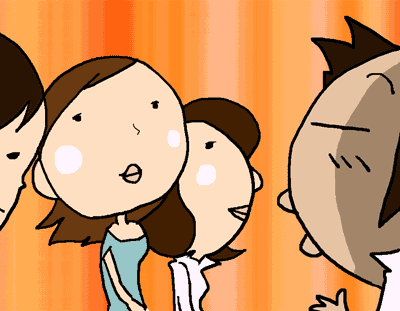

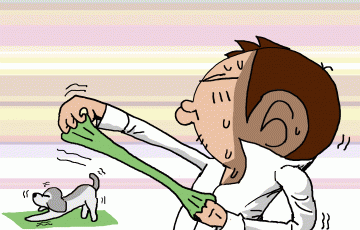
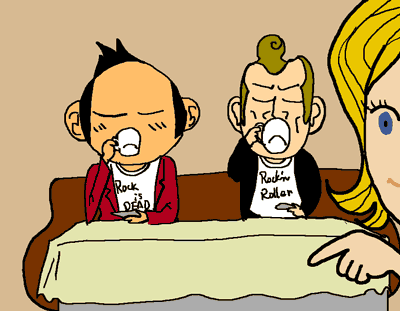

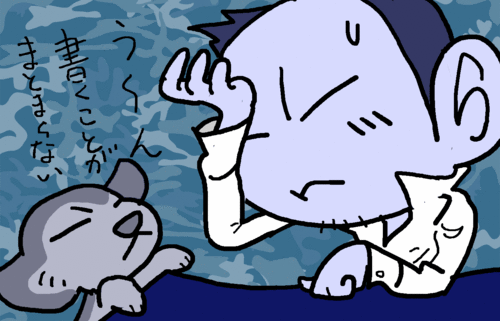



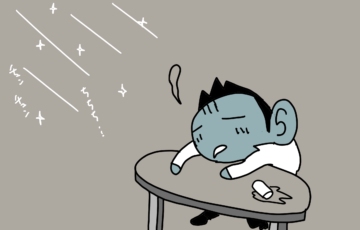
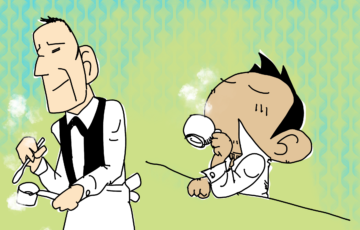
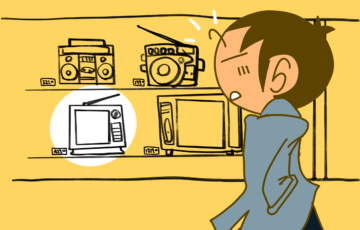
最近のコメント